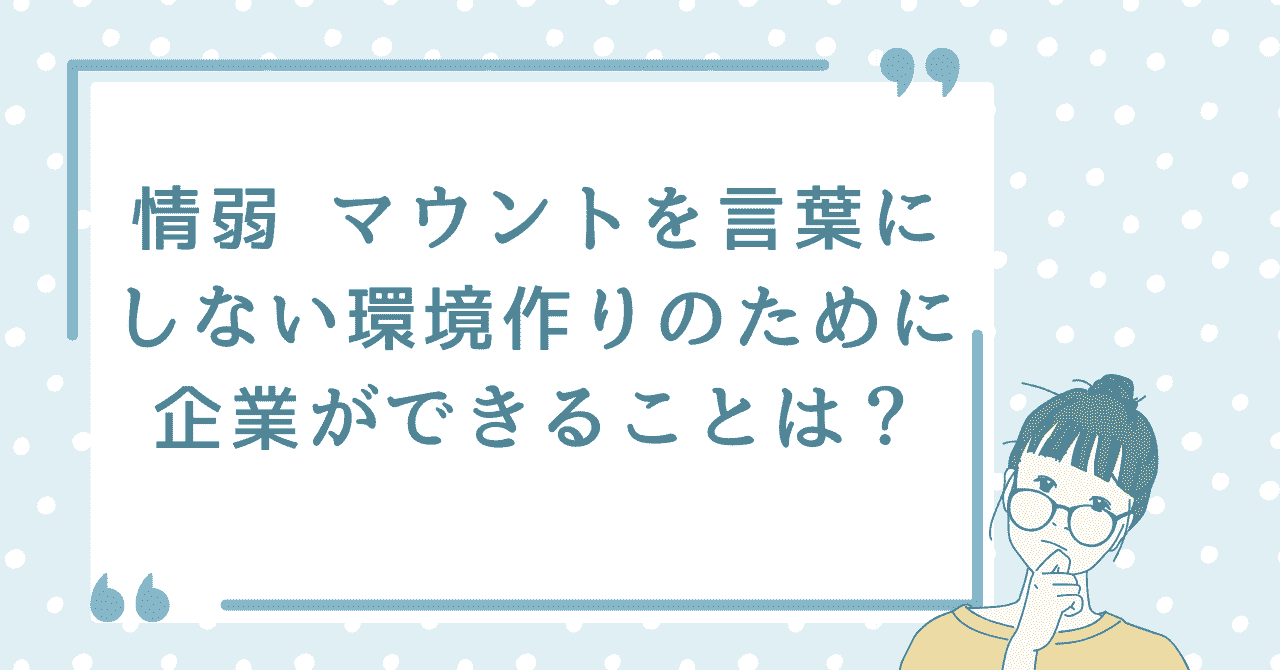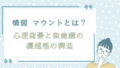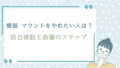「情弱」という言葉は、本来「情報に弱い人」を指す用語ですが、
ビジネスの現場では、知らない人を見下す「マウント行為」と結びつくケースが増えています。
こうしたマウント発言が当たり前になってしまうと、社員が発言しづらくなり、
組織の成長やチームの連携にも深刻な影響を与えることになります。
この記事では、企業が「情弱マウント」を許さない風土を作るために取るべき方針や具体的な施策、
成功事例までをわかりやすく解説します。

情弱マウント、今すぐやめよう!
職場における情弱とマウントの関係とは?問題の本質を理解しよう
情報格差が上下関係やパワーバランスに影響するから

情報へのアクセスの差が、職場の力関係に影響を与えてしまうことがあります。
たとえば、ITツールの使い方に詳しい社員が、そうでない社員を軽んじる場面などがそれに当たります。
本来、業務の成果やチームワークが重視されるべき職場で、
「情報の多さ=優位」という意識が浸透してしまうと健全な関係が築けません。
こうした格差は放置すると、社員の間に目に見えない壁を作ってしまいます。
知識の優劣が評価基準になると対人ストレスが生まれるから

「あの人は詳しいから上」「知らない人は下」という暗黙の評価がある職場では、
常に他人の目を気にする環境が生まれます。
このような職場では、新人や異業種からの転職者が自由に意見を出しにくくなり、ストレスを抱えやすくなります。
知識の差を評価軸にする文化は、長期的には組織の弱体化を招きます。
誰もが安心して学べる環境づくりが求められます。
「知らないこと」が評価や信頼に直結しやすい環境だから

「そんなことも知らないの?」という一言が、相手の自己肯定感を大きく傷つけます。
その結果、社員は「知らないことを隠そう」「質問できない」と感じ、業務効率が下がることになります。
「知らない」を否定しない風土が、結果的にスムーズな情報共有と成長を促します。
すべての社員が「わからないことを聞いていい」と思えることが重要です。

知らないぶん、伸びしろしかないよね!
情弱を見下すマウント発言が職場に与える悪影響
発言しづらい雰囲気が職場全体に広がる

知識に差があることを責められる空気があると、新人や未経験者は発言することを避けるようになります。
その結果、アイデアや意見の多様性が失われ、組織の活力が低下してしまいます。
「誰でも自由に話せる」雰囲気づくりが、マウント対策の第一歩です。
発言の自由は、職場の創造力に直結します。
心理的安全性が失われ、生産性が下がる

Googleの研究でも明らかになっている通り、心理的安全性はチームの生産性に大きく影響します。
「間違っても大丈夫」「知らなくても聞ける」と思える職場でこそ、挑戦や改善が生まれるのです。
マウント発言が多い職場では、挑戦を避ける文化が生まれ、結果的に成果も下がります。
心理的安全性は成果を支える土台です。
優秀な人材が離職につながるリスクがある
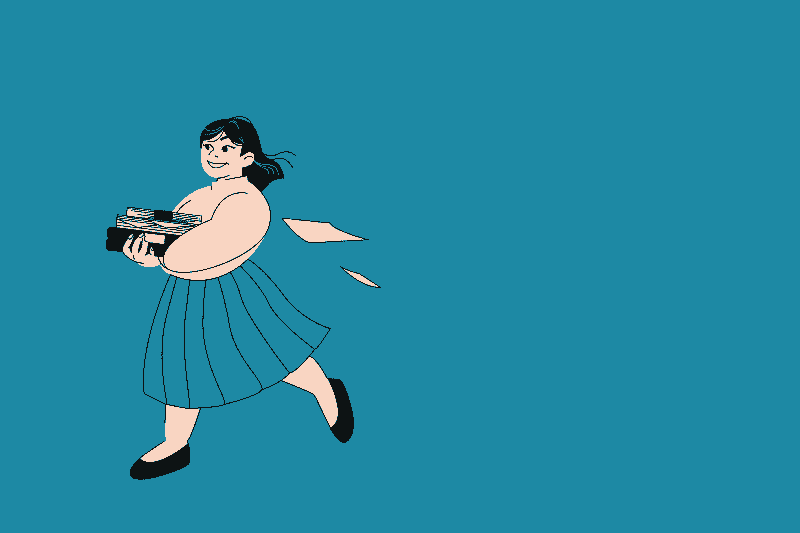
スキルがあっても、コミュニケーションが粗雑な人と働く環境では、
優秀な人ほど早く離れていきます。
特に若手や女性、外国籍の社員などは、「尊重されない」と感じると転職を選びやすくなります。
マウントが当たり前の職場は、長期的に人材の質と量の両面で損失を招きます。
「人を活かす環境」が、採用力にもつながります。
情弱に対するマウントをなくすための企業の基本方針とは
「学び合い・支え合い」の風土を方針に明記する

会社の行動指針やビジョンに、「誰もが学べる」「支え合う文化をつくる」といった文言を盛り込みましょう。
言葉として明示することで、社員一人ひとりの行動にも影響を与えます。
理念と実行が一致することで、文化は根づきます。
形式だけでなく、日々の行動と結びつけることが重要です。
マウント発言をハラスメントとみなす規定を設ける
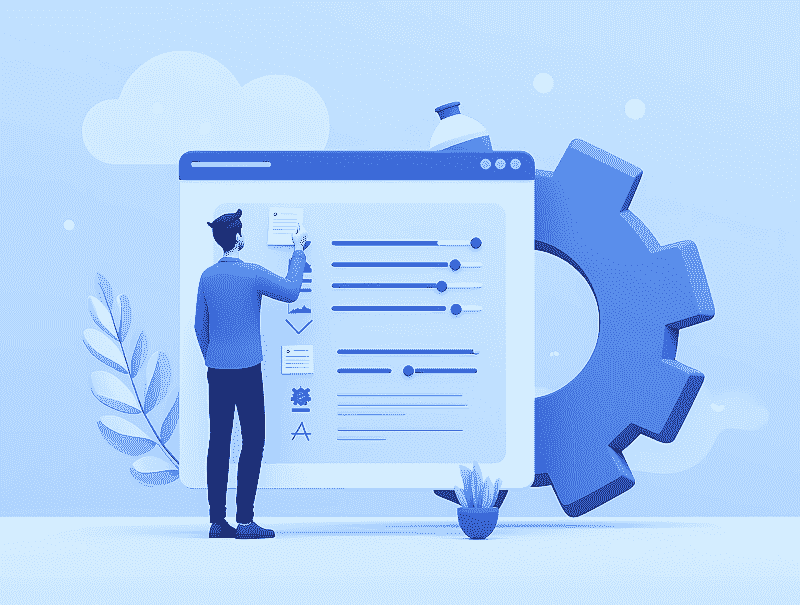
「情弱」という言葉を含むマウント発言も、立派なハラスメントになり得ます。
就業規則や社内ハンドブックに明記し、相談窓口や通報制度とセットで整備することで抑止力が高まります。
「これはハラスメントです」と明確に伝えることが、防止につながります。
ルール化は、行動を変える第一歩です。

「『これハラスメントです』の一言、大切!」
上司も部下も対等に学び続ける姿勢を示す

「年齢や立場に関係なく、学ぶ姿勢が大事」という価値観を、
経営層やマネージャーが率先して示すことが大切です。
「上司でもわからないことを聞ける」職場は、組織全体の風通しを良くします。
学びに上下はありません。
マウントを言葉にしない職場づくりのために企業が取るべき具体策
フィードバック研修を導入する

社員同士が意見を出し合う場面では、無意識のうちにマウントになってしまうことがあります。
「伝え方」や「受け止め方」に関するフィードバック研修を実施することで、丁寧な対話のスキルが育ちます。
「指摘」ではなく「支援」としてのフィードバックを学ぶことが、職場の空気をやわらかくします。
ロールプレイ形式で実践練習を取り入れると効果的です。
心理的安全性を高める1on1ミーティングを実施する
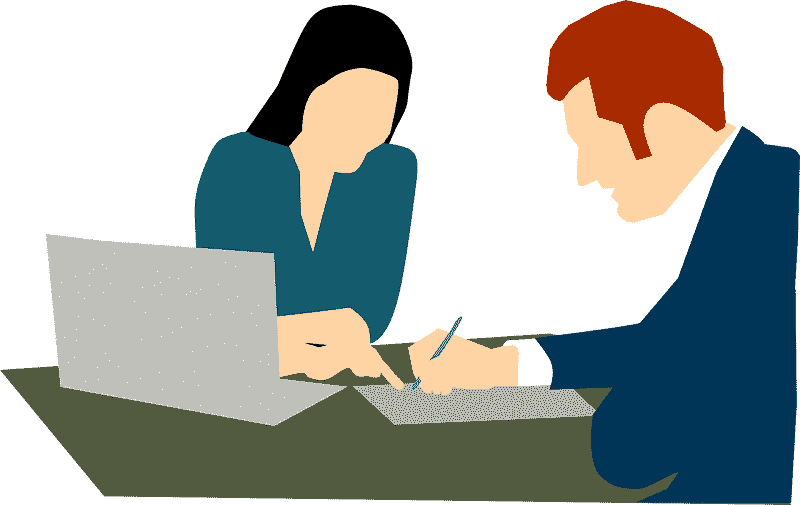
上司と部下が定期的に1対1で対話する「1on1ミーティング」は、信頼関係を築くのに非常に有効です。
業務だけでなく、悩みや学びの不安も共有できる環境をつくることで、マウントを恐れずに発言できるようになります。
「何でも相談できる」関係性が、学びやすい職場を支えます。
上司の聞く力も重要なポイントです。
SlackやTeamsなどで「質問歓迎」チャンネルを設ける
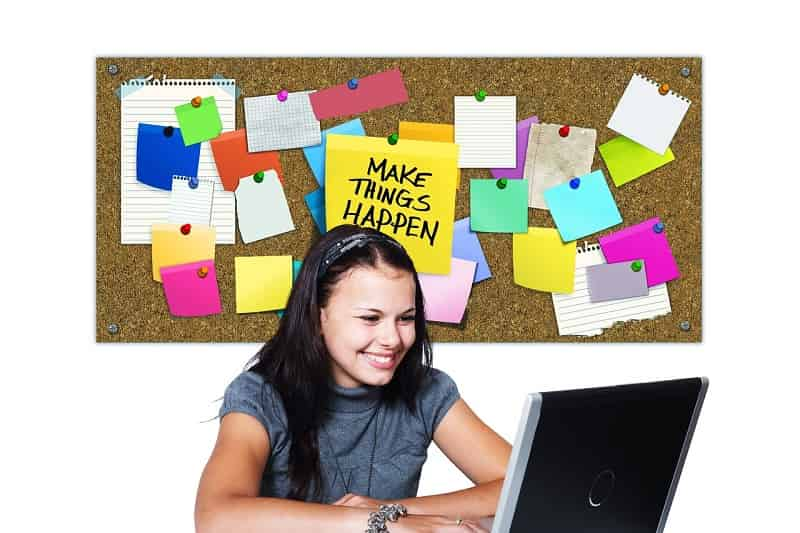
チャットツールを活用し、「初歩的な質問をしていい場所」をあらかじめ設けておくのもおすすめです。
質問が自由にできる場があることで、社員は安心して情報を共有できます。
「知らないことを聞くのは悪いことではない」と全社で共有するメッセージになります。
最初はリーダーが積極的に質問して見本を示しましょう。

質問しやすい環境づくりで安心感アップ!
情弱とされる社員を支援する企業内の教育とサポート体制
ITスキル・情報リテラシー研修を定期開催する

「知らない」ことがマウントの原因になるなら、知る機会を平等に与えることが一番の対策です。
社内でITスキルやデジタルツールの使い方を学べる研修を定期的に開催しましょう。
初心者でも参加しやすい内容と雰囲気が大切です。
講師に社内メンバーを活用するのも良い方法です。
ピアサポート制度で社員同士の学び合いを促す

ピアサポート制度とは、同僚同士が教え合い・支え合う仕組みです。
年齢や部署に関係なく、「質問しやすい人」を見える化するだけでも、安心感が生まれます。
同じ目線で学べる仲間の存在が、職場の心理的障壁を下げます。
「教えること」は教える側の成長にもつながります。
OJTだけでなく動画やeラーニングも活用する

対面だけでなく、自分のペースで学べる教材を用意することも重要です。
社内の業務マニュアルや操作動画を整備すれば、何度でも見返すことができるため、聞きにくい内容もカバーできます。
「聞きづらい」を「自分で確認できる」仕組みがあることで、マウントの温床をなくせます。
ナレッジ共有の仕組みは、企業資産にもなります。
マウントを助長しない企業文化を作るためのコミュニケーションの工夫
「知らない」を肯定するメッセージを組織で発信する
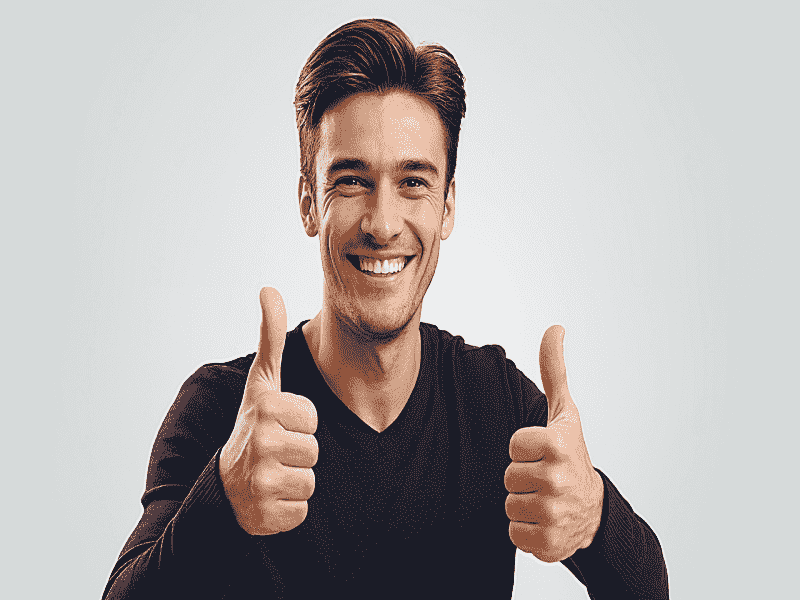
「知らないからこそ学べる」「誰でも初めてがある」といった言葉を、
社内報や朝礼などで継続的に発信しましょう。
公式なメッセージとして示すことで、社員は安心して学びを楽しめるようになります。
社長や管理職が言葉にすることが特に効果的です。
上司が率先して質問やミスを共有する文化をつくる
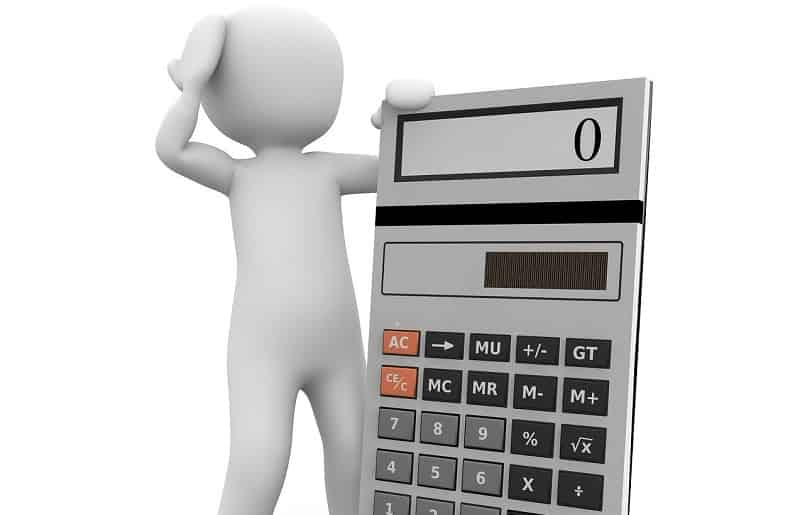
部下は上司の行動をよく見ています。
上司が自ら「これ知らなかった」「最近失敗した」と共有することで、
「完璧じゃなくても大丈夫」という空気が職場に広がります。
ミスを共有できる職場は、学びのスピードが早い組織になります。
失敗は学びのきっかけです。

完璧求めず、失敗はみんなの学びに!
感謝や承認を伝えるフィードバックを習慣化する
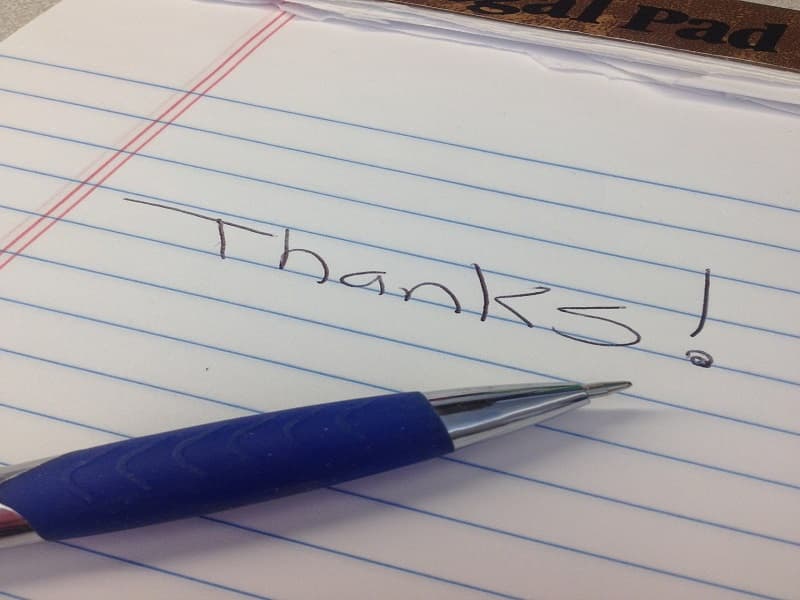
社員が努力したことに対して、「ありがとう」「助かったよ」と伝える習慣をつくることも大切です。
相手を認める言葉が増えると、自然とマウントは減っていきます。
承認の文化が、人間関係を前向きに変えていきます。
ポジティブな職場にはマウントが入り込む隙がありません。
情弱とマウント問題に取り組む企業事例と成功のポイント
メルカリの心理的安全性を重視した「バリュー」浸透策

メルカリでは、「心理的安全性」を経営方針の中核に据え、「All for One」「Be a Pro」などのバリューを全社員に浸透させています。
それにより、誰もが安心して発言・質問できる風土を実現しています。
行動指針を具体化し、現場で体現することで、企業文化として根づきました。
サイボウズの多様な価値観を認め合う風土づくり

サイボウズでは、「100人100通りの働き方」を掲げ、
多様なスキルやバックグラウンドを持つ人材が活躍できる組織を実現しています。
「知らない」「できない」を否定しない雰囲気が、チャレンジを後押ししています。
ダイバーシティが、マウントをなくす最大の武器になります。
Sansanの社内ナレッジ共有制度「Know Who」で情報格差を減らす

Sansanでは、誰が何に詳しいのかを社内で可視化し、いつでも相談できる体制を整えています。
この「Know Who」は、質問のハードルを下げ、情報の偏りを解消するのに役立っています。
ナレッジの見える化が、情報格差によるマウントを未然に防ぎます。

Know Whoで情報の壁が一気に低くなりました!
まとめ|情弱 マウントを許さない職場環境を企業が目指すべき理由
多様性と心理的安全性がイノベーションにつながる

いろいろな立場や背景を持つ社員が、安心して意見を出し合える環境が、結果的に新しい価値を生み出します。
マウントのない職場こそ、多様性と創造性が花開く場です。
マウントのない職場は人が成長しやすい

誰もが自分のペースで学び、成長できる職場は、結果的にチーム全体の力も高まります。
上司も部下も一緒に成長していく姿勢が、組織の質を変えていきます。
「学び合う職場」が持続的な組織の力をつくる

マウントではなく、学び合い・支え合いが文化となることで、長く強いチームを育てることができます。
企業が目指すべきは、「誰もが安心して学べる場所」です。