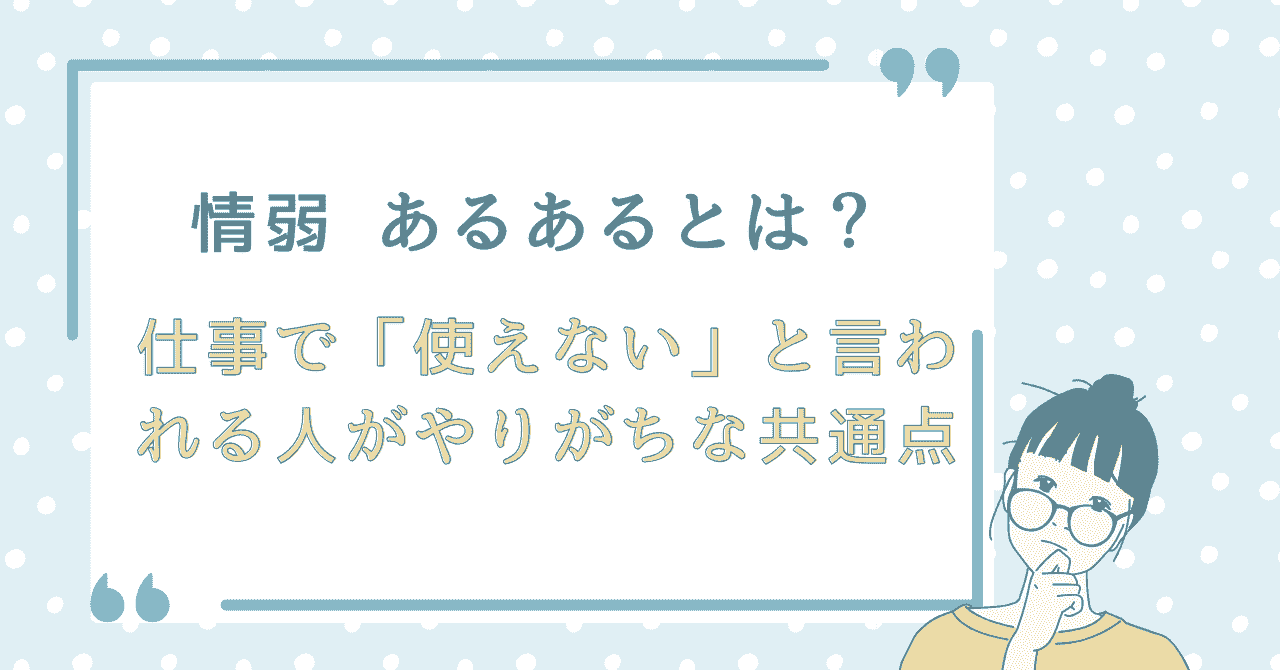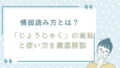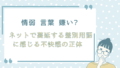職場で「この人、使えないな…」と思われてしまう原因には、ある共通点があります。
それが「情弱」的な行動です。
情弱とは、情報に弱く、自分で調べたり考えたりする力が不足している人を指す言葉です。
この記事では、仕事で「情弱」と見なされてしまう人の特徴や行動パターンを解説し、
どうすればそこから抜け出して「使える人材」になれるかをわかりやすく紹介していきます。
もしあなたが「最近、職場で浮いている気がする」「評価が低いかも」と感じているなら、
ここで紹介する「情弱あるある」に思い当たる節があるかもしれません。
ぜひ最後まで読んで、自分を見つめ直すきっかけにしてください。

“情弱”を脱出して、仕事力アップ!
情弱とは?仕事でよく見られる情弱あるあるを知ろう
ネットやITに弱く基本的な操作ができない
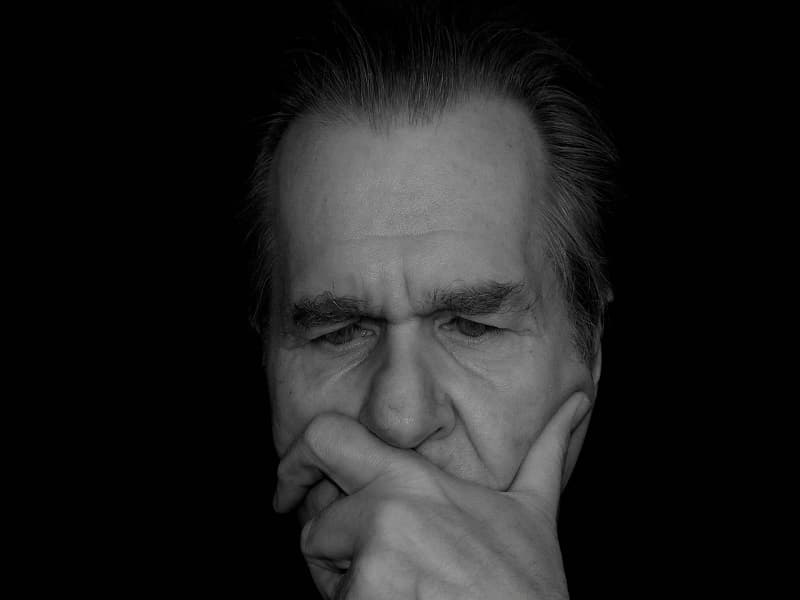
パソコンの操作や、オンラインツールの使い方が極端に苦手な人は、
職場で「情弱」と見なされやすいです。
たとえば、ブラウザのタブを開けない、Zoomでマイクのオンオフがわからないなど、
基本操作すら怪しい場合は要注意です。
今の時代、どんな職種でもITスキルは必要不可欠です。
業務に必要な最低限の知識すらないと、
「教える手間がかかる」「作業が遅い」と思われてしまいます。
「私はアナログ派だから」では通用しない時代になっていることを自覚する必要があります。
まずは基本的なITスキルを独学で学ぶ意識が大切です。
指示を待つだけで自分から動かない

仕事を進める上で「指示がないと動けない人」も情弱と見なされがちです。
常に受け身で、自分からやるべきことを探さないと、「使えない」と思われるのは当然です。
上司やチームは、自分で考えて行動できる人材を求めています。
たとえ新人であっても、自分なりに考えた上で質問したり、提案したりする姿勢が求められます。
指示が来るのを待っているだけでは、成長のチャンスも逃してしまいます。
「自分から動ける人」になれば、周囲の信頼も一気に高まります。
業務の背景や目的を理解しようとしない

目の前の作業だけをこなして、「なぜこれをやるのか」を理解しようとしない人も、評価されにくいです。
業務には必ず目的や意図があります。
背景を理解している人と、していない人では、同じ作業でも成果に差が出てきます。
「とりあえずやればいい」という姿勢は、信頼を失う原因になります。
常に「これは何のための仕事なのか?」と自分に問いかける習慣を持つことが大切です。
自分で調べず何でもすぐ人に聞く
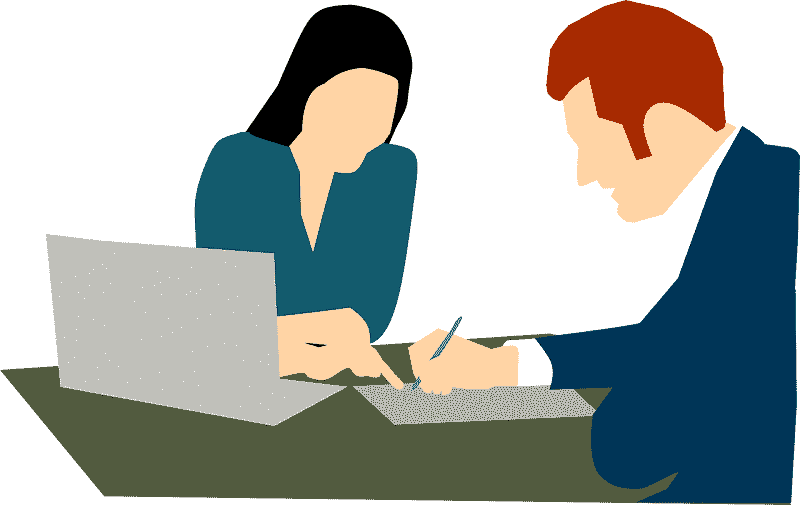
分からないことがあると、すぐに「〇〇さん、これ教えてください」と聞く人がいます。
もちろん、質問すること自体は悪いことではありません。
ただ、「一度も調べていない」のが見え見えだと、周囲の人はイラッとします。
聞く前に5分でも調べてみる姿勢があるかないかで、印象は大きく変わります。
まずは自分で検索し、それでも分からない時に質問することで、相手の負担も減り、
学びも深まります。

質問前にまず自分で5分ググってみよう!
職場での情弱あるある:使えないと思われる行動パターン
エクセルやスプレッドシートが使えない

エクセルやGoogleスプレッドシートは、ほぼすべての業種で使われているツールです。
関数が使えなくても最低限、データの入力、並び替え、フィルターくらいは使える必要があります。
基本的な操作すら怪しい人は、「いつまでも任せられない」「教えるのが面倒」と思われます。
YouTubeや学習サイトで無料で学べるので、使い方を覚える努力をしましょう。
社内チャットの基本マナーが守れない

チャットの挨拶をしない、文章が長すぎて読みにくい、スタンプだけで返事するなど、
チャットのマナーを知らない人も要注意です。
ビジネスチャットはメールと同様に、情報伝達の手段として非常に重要です。
読み手のことを考えた簡潔で礼儀正しい文章を心がけましょう。
「チャットだから適当でいいや」は通用しません。
社内ポータルやマニュアルの存在を知らない

多くの会社では、業務マニュアルやFAQが社内ポータルに用意されています。
しかし、情弱な人ほど「そんなのあったんですか?」と平気で言います。
まずは社内でどんな情報がどこにあるのかを把握することが大切です。
ポータルをこまめにチェックするだけで、わからないことの8割は解決できます。

ポータルこそ隠れた宝の山、毎日チェックしてね!
メールの返信が遅く、要点が伝わらない

メールの返信が遅かったり、長文で要点が分かりにくいと、相手の時間を奪ってしまいます。
特にビジネスメールは、迅速で簡潔、そして丁寧であることが求められます。
情弱な人は、どんなメールでも「了解しました」の一言だけで済ませがちです。
相手の立場を想像して、必要な情報をきちんと含めた返信を心がけましょう。
情弱あるあるに当てはまると「使えない」と評価される理由
自分で考えず業務効率が悪くなるから

情弱な人は、自分で考える習慣がないため、何をするにも時間がかかり効率が悪くなります。
たとえば、作業の順番を考えずに手を付けるため、無駄な動きが増えてしまいます。
「どうすれば早く終わるか」「この作業に必要なことは何か」を考えることが、
効率アップの第一歩です。
自分の作業が他の人にも影響を与えることを意識しましょう。
チーム全体の足を引っ張ることになるから
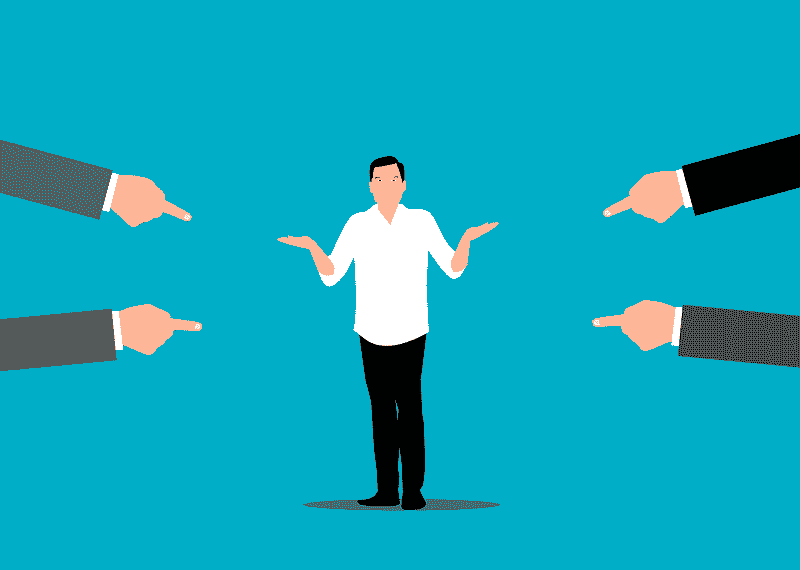
仕事は一人で完結するものではありません。
誰かの遅れやミスは、チーム全体に影響します。
情弱な人の行動は、結果として周囲の負担を増やすことになります。
「この人がいると遅れる」と思われたら、重要な仕事は任せてもらえなくなります。
チームの中での自分の役割をきちんと理解し、責任を持って行動することが大切です。
サポートの手間が増えて周囲の負担になるから

情弱な人に何度も同じことを教えなければならない状況は、周囲にとって大きなストレスになります。
「この人に教えると時間がかかる」「また聞かれそうだな」と思われると、
サポートする側も消耗してしまいます。
一度教わったことはメモを取り、自分で再現できるようにする努力が必要です。
そうすることで、周囲の負担も減り、自分の信頼度も高まります。

教えたらメモで定着!疲労も激減だよ
信頼して仕事を任せられないから
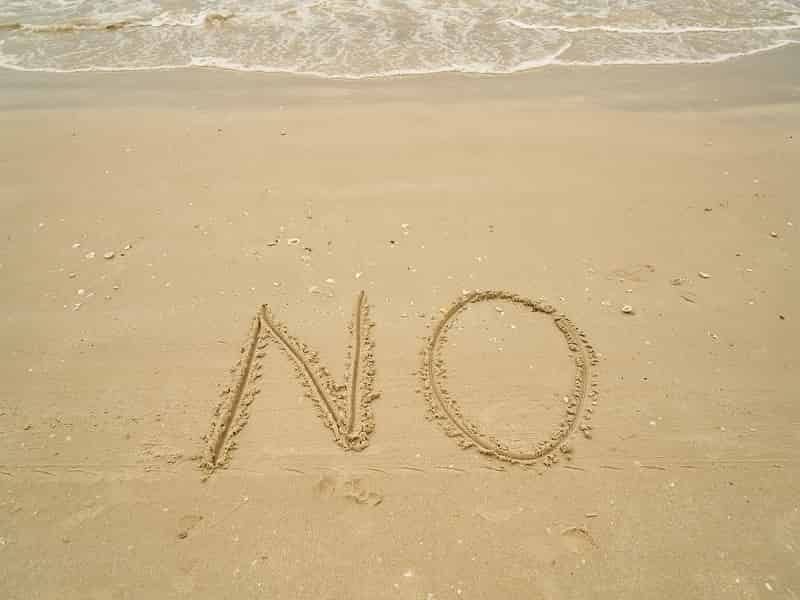
仕事は「この人なら任せられる」と思ってもらえるかどうかが大切です。
情弱な行動が目立つと、「また何かやらかすかも」「任せるのが怖い」と判断され、
重要な仕事を振ってもらえなくなります。
信頼されるためには、ミスを減らし、学ぶ姿勢を見せることが必要です。
小さなことでも着実にこなしていけば、信頼は自然とついてきます。
上司や同僚が感じる情弱あるあるな行動とは?
基本用語を知らずに会議についていけない

業界や社内でよく使われる基本用語を知らず、会議でポカンとしてしまう人は少なくありません。
たとえば「KPI」や「PDCA」など、最低限のビジネス用語は知っておくべきです。
会議中に聞き慣れない言葉が出たら、後で調べて理解する習慣をつけましょう。
会議に出る前に、使われそうな単語を事前に調べておくことも効果的です。
報告・連絡・相談(ホウレンソウ)ができない
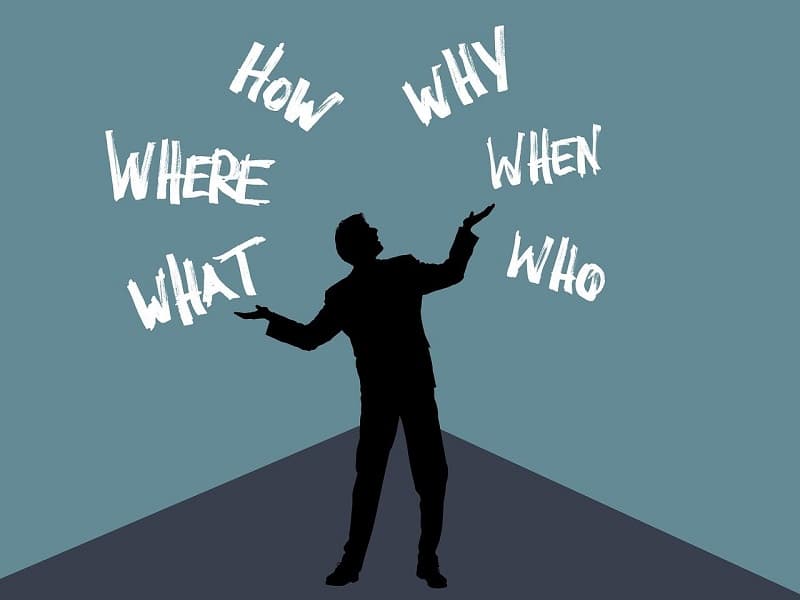
何かトラブルが起きても報告せず、周囲に迷惑をかける…これは典型的な情弱あるあるです。
ホウレンソウができない人は、周囲から「信用できない」「フォローが必要」と判断されがちです。
進捗や問題があるときは、早めに上司に共有しましょう。
ホウレンソウができるだけで、仕事の信頼感は一気に上がります。
業務ツールの使い方を覚えようとしない

社内で使っている勤怠管理システムやチャットツールなど、ツールの使い方を覚えず、
毎回「これってどうやるんでしたっけ?」と聞く人もいます。
このような態度は、「学ぶ気がない」「やる気が感じられない」と取られてしまいます。
1回教わったらメモを取り、繰り返し操作して覚えることが大切です。
ツールの使い方がスムーズになると、業務も効率化します。

一度学んだらメモ→反復で即マスター!
注意されるとすぐに落ち込んでしまう

ミスを指摘されると、ふてくされたり、黙り込んだりする人がいますが、
これは非常にマイナスな印象を与えます。
注意はあなたの成長のために行われるものであって、人格を否定するものではありません。
むしろ、素直に受け入れ、「次から気をつけます」と前向きに返す人の方が評価されます。
落ち込みすぎず、改善する姿勢を見せることが大切です。
情弱あるあるを脱却して「使える人材」になるには?
まずは「ググる力」を身につける
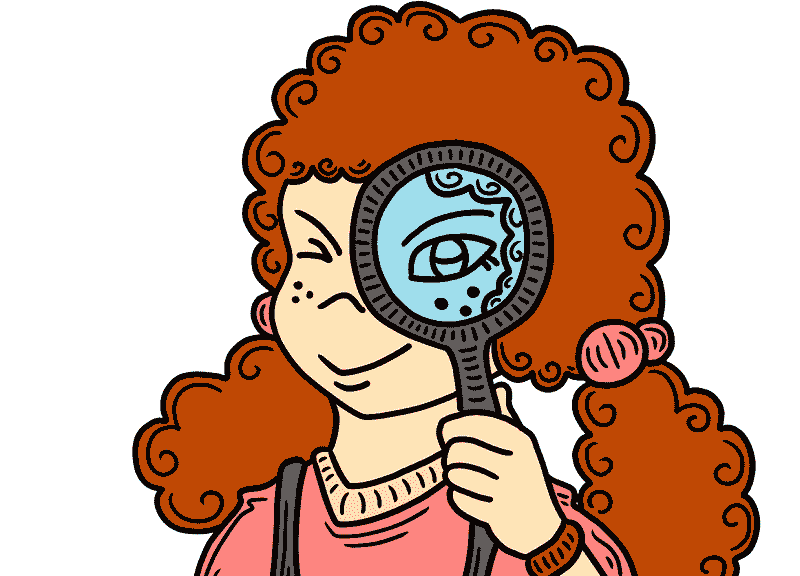
わからないことがあったら、まず自分で調べる癖をつけましょう。
Googleで検索する力、いわゆる「ググる力」は現代の必須スキルです。
「エラーコード 意味」「Zoom 音が出ない」など、
具体的に検索するだけで多くの情報が得られます。
検索スキルを身につけることで、他人に頼らず問題解決できる力がつきます。
基本的なビジネスツールの使い方を学ぶ
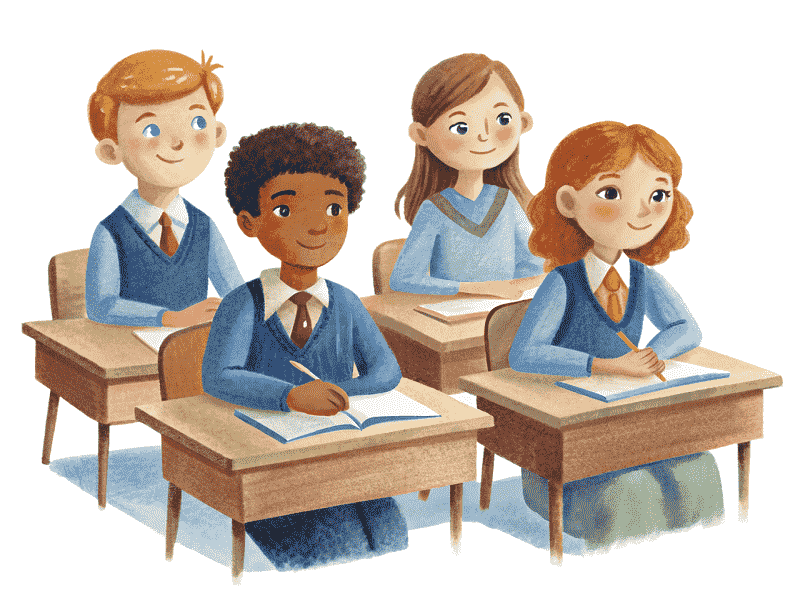
エクセル、チャット、メールなど、日常業務で使うツールの使い方は、最低限マスターしておくべきです。
YouTubeや学習サイトで基礎講座を無料で学べる時代なので、自分に合った方法で学びましょう。
「知らない」ではなく、「学ぶ意思」があるかどうかが評価のポイントになります。
1日10分でも継続すれば、必ずスキルは上がります。
仕事の全体像を意識する癖をつける

目の前のタスクだけでなく、「この仕事は何のためにやっているのか?」を考える癖をつけましょう。
背景や目的が分かると、判断力がつき、応用も利くようになります。
上司の指示の意図を読み取れるようになると、「使える人材」として重宝されます。
全体を見渡す意識を持つことで、質の高い仕事ができるようになります。

「『なぜ』を意識すると仕事の幅がグンと広がる!」
質問する前に一度は自分で調べる

「すぐに聞く」ではなく、「まず調べてから聞く」が信頼されるコツです。
たとえ分からなくても、「こういうことを調べたけど分からなかった」と言えば、
相手も教えやすくなります。
調べた記録や思考の過程を示すことで、学ぶ姿勢も伝わります。
質問の仕方一つで、評価は大きく変わります。
情弱な人によくある「情報収集の苦手さ」とは
検索キーワードの選び方がわからない

「何て検索すればいいのかわからない」という人は意外と多いです。
ポイントは、自分の疑問をシンプルな単語に分解し、組み合わせることです。
例えば「PDFが開けない」ときは「PDF 開かない 原因」といった検索が有効です。
検索ワードの使い方を知るだけで、情報収集の精度が大きく変わります。
信頼できる情報源とそうでないものの区別がつかない

インターネットには正確な情報もあれば、古くて誤った情報も混在しています。
信頼できるサイト(企業の公式ページや大手メディア)かどうかを見極める目を持ちましょう。
情報の発信者・日付・実績などを確認する癖をつけることが大切です。
誤った情報に惑わされないためにも、メディアリテラシーを高めましょう。
必要な情報を整理してメモできない
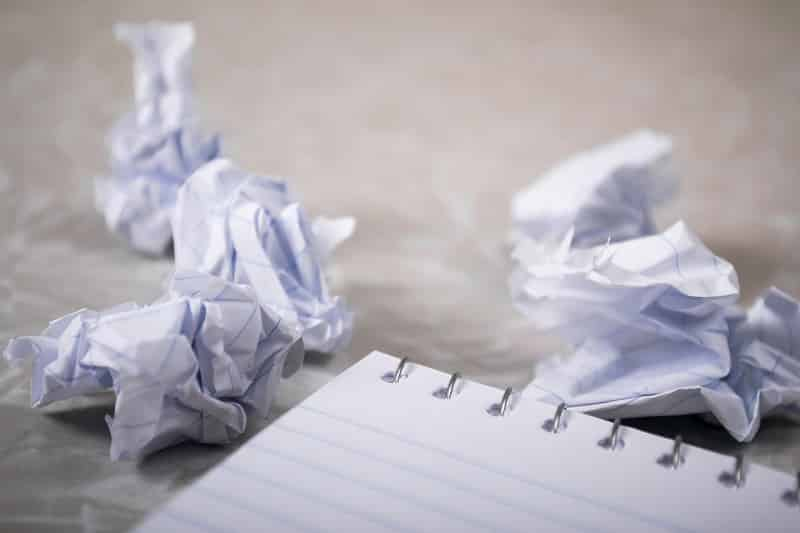
せっかく情報を得ても、それを整理・記録しなければすぐに忘れてしまいます。
重要な内容はメモ帳やノート、デジタルツールなどを使って記録しておきましょう。
整理された情報は、繰り返し見ることで知識として定着します。
「何を調べたか」「どう解決したか」をメモする習慣が、自分の成長につながります。
新しい情報にアンテナを張れない
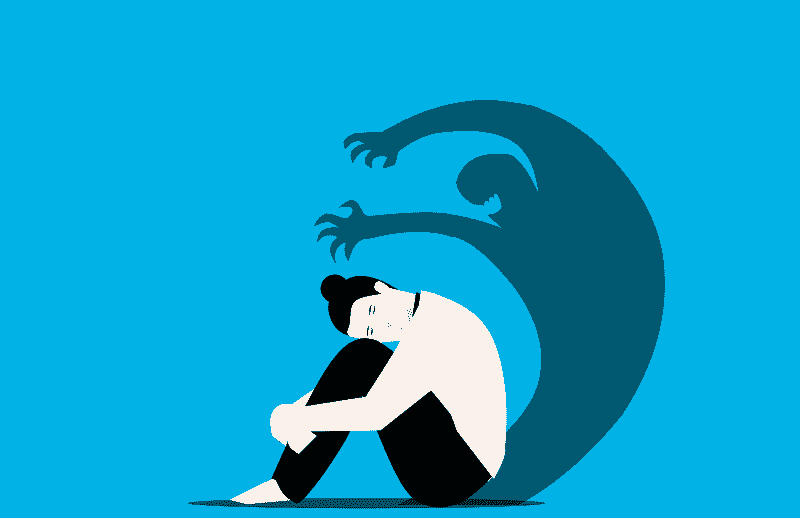
日々進化するビジネス環境では、常に最新の情報に触れていることが重要です。
情弱な人は「興味がない」「自分には関係ない」と感じて情報をシャットアウトしてしまいがちです。
業界ニュースや新しいツール情報には、積極的に目を向けましょう。
最新情報に敏感な人ほど、現場で信頼されやすい傾向があります。

アンテナ張って情報キャッチ!
情弱あるあるを改善するための簡単な習慣とは
毎朝ニュースアプリで業界情報をチェックする

毎朝5分だけでも、業界に関するニュースに目を通す習慣をつけましょう。
スマホに「NewsPicks」「SmartNews」「Yahoo!ニュース」などのアプリを入れておけば、
手軽に最新情報をチェックできます。
継続して読むことで、業界の流れやキーワードに強くなり、会議や商談での理解度も格段にアップします。
朝の通勤時間やコーヒーを飲みながらのひとときに、情報収集の時間を取り入れましょう。
GoogleやYouTubeで分からないことを検索する習慣をつける
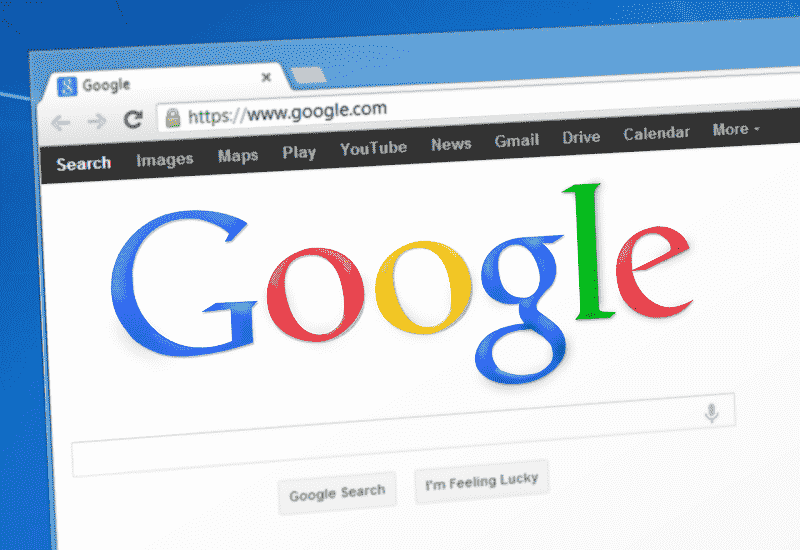
何か分からないことがあったら、まずはGoogleかYouTubeで調べてみましょう。
特にYouTubeには、初心者向けの解説動画が豊富に揃っており、視覚的に学びやすいです。
「エクセル 初心者 関数」「Googleドキュメント 使い方」などのキーワードで検索すれば、
すぐに役立つ情報が手に入ります。
調べることが当たり前になると、自然と「情弱」とは呼ばれなくなります。
社内ツールのマニュアルを読み直す
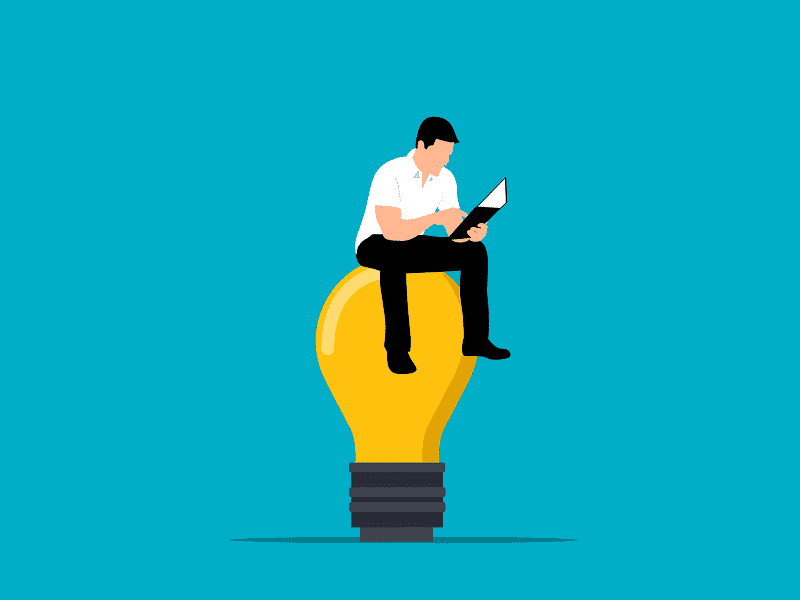
多くの企業では、社内ポータルや共有ドライブに業務マニュアルが用意されています。
「めんどくさいから」と読まずに放置している人は、それだけで大きな損をしています。
1日1つのツールを読み直すだけでも、知らなかった便利な機能や効率化のヒントを得られます。
分からないことがあったら、まずマニュアルを探してみる癖をつけましょう。
日報やメモをこまめに書くようにする
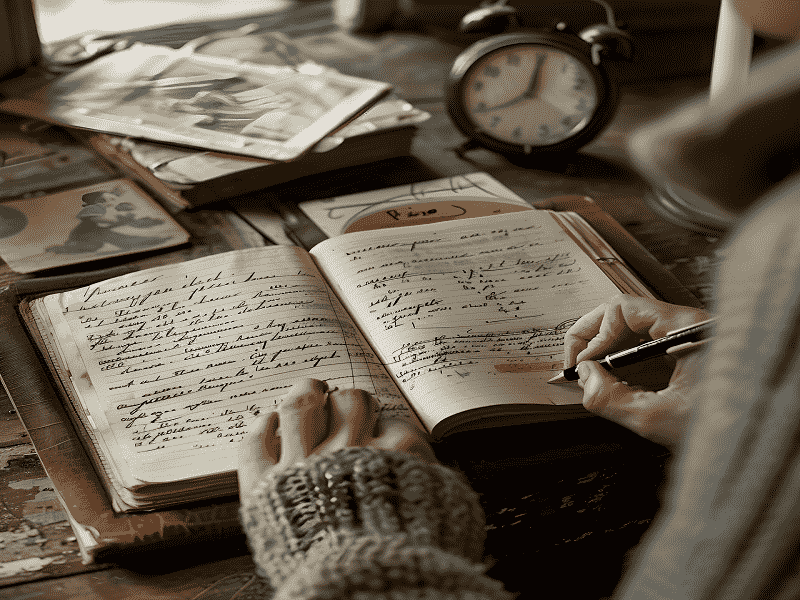
日々の業務内容や気づきを日報やメモに残すことで、情報を整理する力が身につきます。
また、後で見返すことで「前はどうやって対応したか」がすぐに思い出せるようになります。
記録を残すことで、思考の整理とスキルの定着が促進されます。
「書く」ことは、「学ぶ」ことと密接に関係しているのです。

日々のメモで自分成長が一目瞭然!
まとめ:情弱あるあるから脱却して仕事で「使えない」と言われないために

情弱あるあるは、誰にでも当てはまる可能性がある行動パターンです。
しかし、だからこそ、日々の小さな意識と行動の積み重ねで、改善することが可能です。
「ネットやツールが苦手」「自分で考えるのが面倒」と感じていたとしても、
まずはできることから一歩ずつ始めていくことが大切です。
まずは、わからないことがあったら自分で調べる。
次に、業務の背景を意識して動く。
そして、情報収集の習慣を取り入れる。
これだけでも、周囲からの見られ方は確実に変わっていきます。
情弱から脱却して、「信頼される人材」「使える人材」になることは、
決して難しいことではありません。
今日から少しずつ、変わる努力を始めてみましょう。