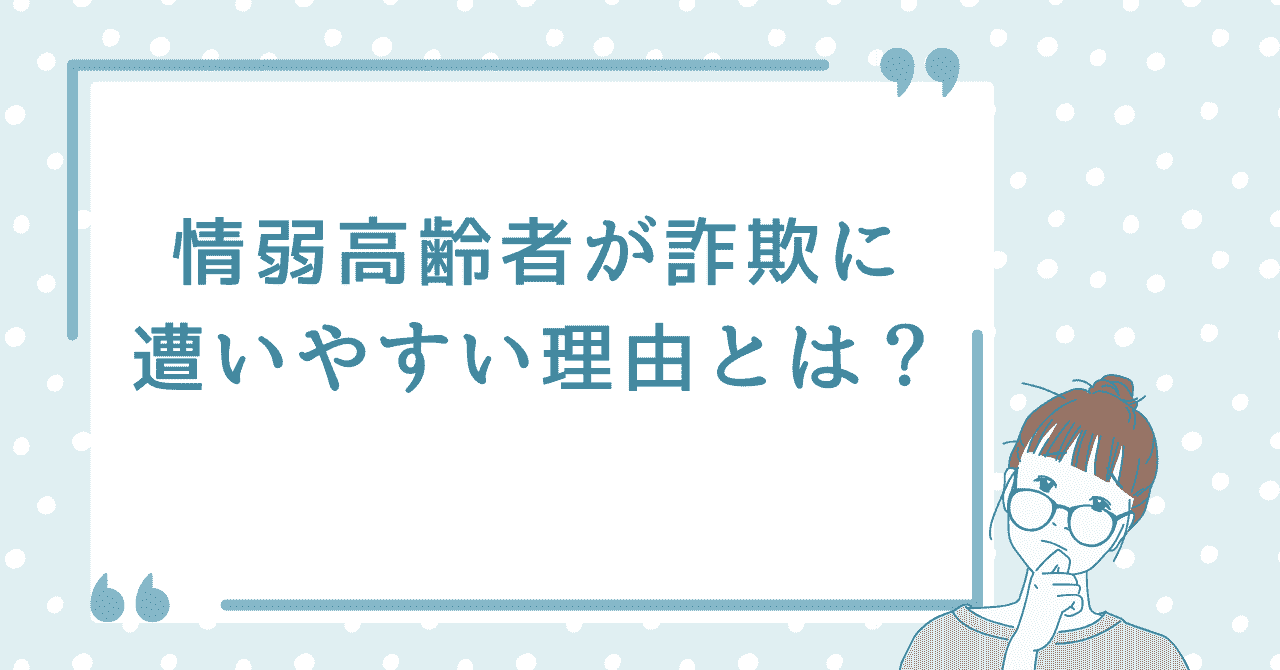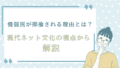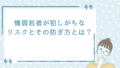近年、高齢者を狙った詐欺被害が急増しています。
中でもインターネットやスマホの知識が少ない“情報弱者(情弱)”な高齢者は、
特にターゲットにされやすくなっています。
この記事では、情弱な高齢者がなぜ詐欺に遭いやすいのか、その原因と手口、
そして被害を未然に防ぐための対策を詳しく解説します。
ご自身が高齢の方、ご家族に高齢者がいる方のどちらにも役立つ情報をまとめていますので、
ぜひ最後までご覧ください。

高齢者も家族も一緒に防犯意識UP
情弱な高齢者が詐欺に狙われやすい背景とは
インターネットやスマホに不慣れだから
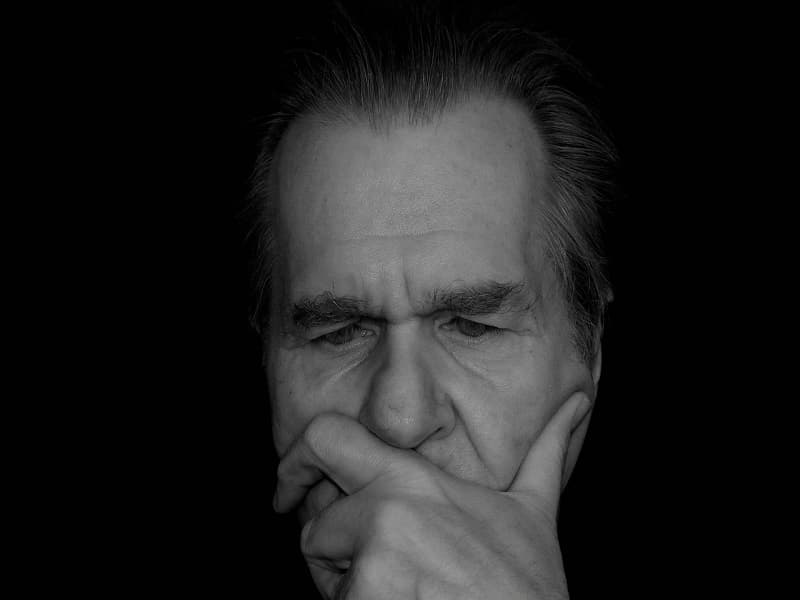
現代の詐欺の多くは、スマホやインターネットを利用して行われています。
しかし、多くの高齢者はそうした機器の操作や仕組みに慣れていません。
そのため、警告画面や偽サイトを見ても「本物」と思い込み、
詐欺に引っかかってしまうケースが多く見られます。
「知らない」「よく分からない」が詐欺師の狙い目になっているのです。
一人暮らしで孤独を感じているから
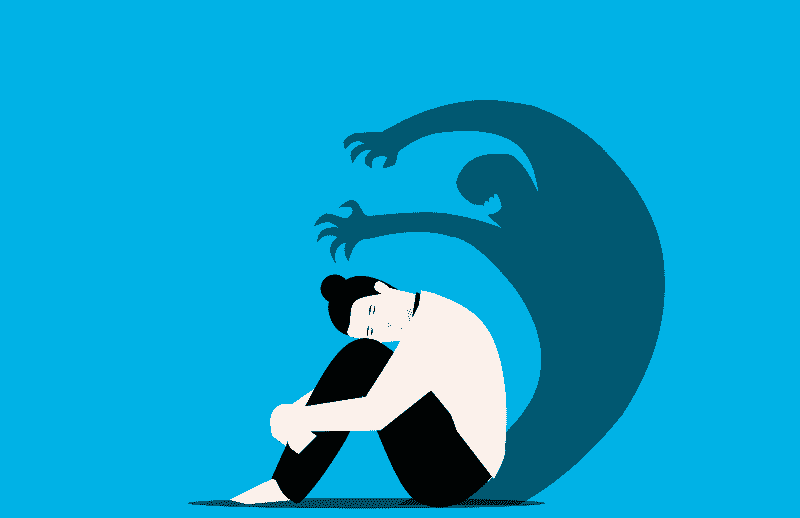
一人暮らしの高齢者は、誰かと会話する機会が少ないため、
ちょっとした電話や訪問でも話を聞いてしまいがちです。
特に詐欺師は、そうした孤独な心につけ込んで優しく話しかけ、
信頼させてから騙す手口を使います。
最初はただの世間話から始まり、少しずつ詐欺行為へと誘導してくるのが特徴です。
話し相手がいないという状況自体が、詐欺に巻き込まれるリスクを高めています。

「優しい言葉に潜む罠に注意!」
世間話のような電話にも警戒心が薄いから

「こんにちは、お元気ですか?」といった、親しげな電話が突然かかってくることがあります。
これは詐欺の前兆であり、警戒すべきサインです。
しかし、電話を受ける側は「誰かの紹介かな?」「良い人そうだな」
と警戒せずに話を続けてしまいます。
この油断が、詐欺被害の第一歩となってしまうのです。
なぜ情弱な高齢者は詐欺のターゲットになりやすいのか
最新の詐欺手口を知らないから
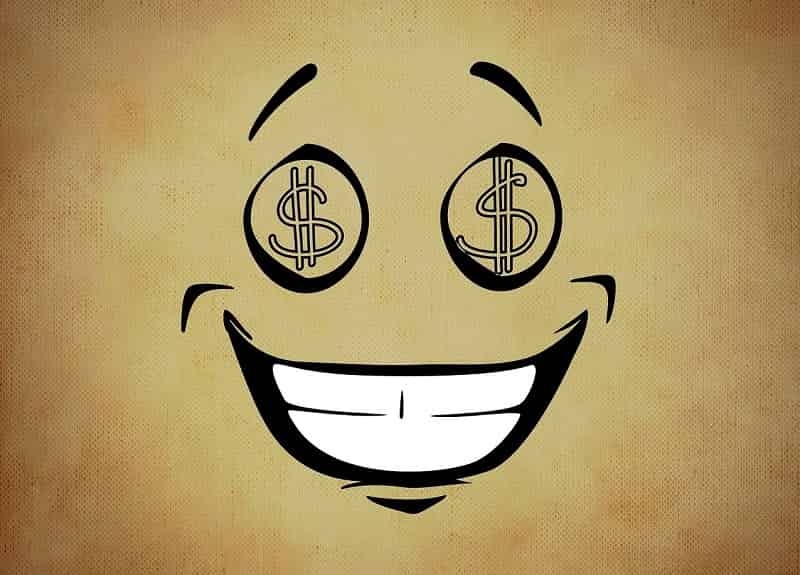
詐欺の手口は年々進化しています。
たとえば、「家族を装う」「自治体や金融機関を名乗る」「スマホを操作させる」など、
巧妙な方法が次々と登場しています。
テレビや新聞を見ていても、すべての詐欺情報をカバーするのは難しく、
ネットを活用できない高齢者は取り残されがちです。
知らない=防げない、という状態が危険なのです。
「信じやすさ」を狙われてしまうから
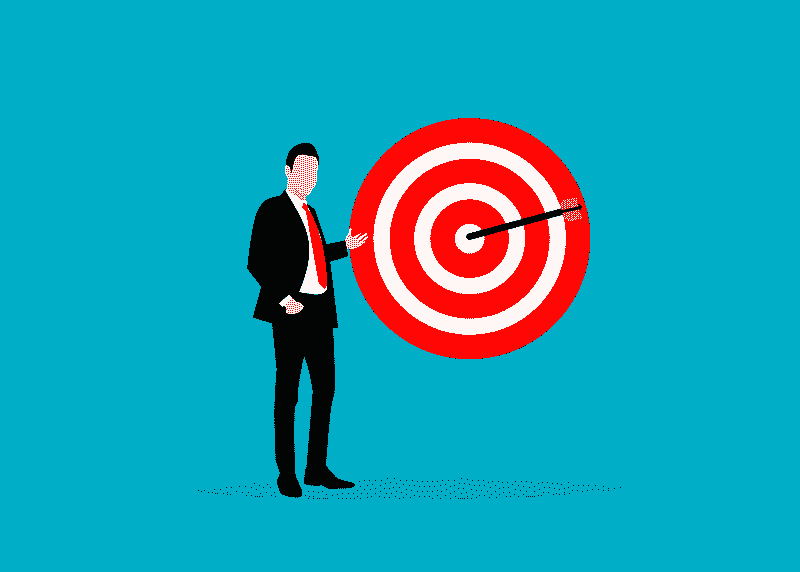
高齢者の多くは、人を信じやすいという特徴があります。
「困っている人を助けたい」「まさか自分が騙されるなんて」と思ってしまい、
詐欺に気づけないのです。
詐欺師はその心理を熟知しており、丁寧な口調や優しい言葉で信頼を得ようとします。
「信用させる」が詐欺の第一歩であることを知る必要があります。
家族との連絡が少なく判断を一人でするから

詐欺に遭う高齢者の多くは、相談せずに一人で決断してしまっています。
「子どもは忙しそうだし…」「こんなことで迷惑をかけたくない」と思い、
誰にも言わずに行動してしまうのです。
しかし、そこで家族や信頼できる人に一言でも相談できていれば、防げたケースは数多くあります。
小さな判断も、できるだけ共有することが大切です。

「迷ったらまず一声かける習慣を」
情弱な高齢者が陥りやすい詐欺の手口とは
オレオレ詐欺(家族を装って金銭を要求)

「オレだよ、オレ」と家族を名乗り、お金を要求する詐欺です。
声が違っていても「風邪をひいてる」「電話を変えた」などの言い訳で信じさせます。
さらに「事故を起こした」「会社に迷惑がかかる」と不安をあおり、
現金を振り込ませたり、直接取りに来ることもあります。
家族と合言葉を決めておくなどの対策が有効です。
還付金詐欺(税金や保険料の返金を装う)
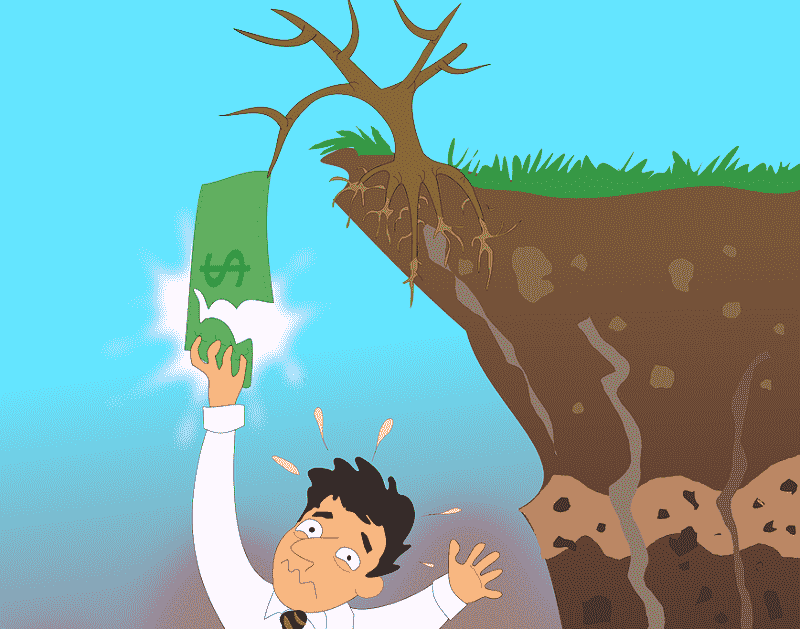
「医療費が戻ります」「年金の過払いがあります」と言って、ATMへ誘導する詐欺です。
金融機関や市役所の職員を装い、親切なふりをしてお金を騙し取ります。
本来、ATMでお金が「返ってくる」ことはありません。
ATMでの操作を求められたら、それだけで詐欺だと疑いましょう。
スマホやパソコンのサポート詐欺

「あなたのスマホがウイルスに感染しています」という警告画面を表示し、
偽のサポートセンターに電話をかけさせる手口です。
電話をかけると「今すぐ修復できます」「アプリを入れてください」と言われ、
遠隔操作で個人情報やお金を奪われます。
本物の警告は、電話番号を表示しません。
画面に表示された番号に電話してはいけません。
不安なときは、家族や詳しい人に確認してもらいましょう。

慌てて番号にかけない!冷静第一
「必ず儲かる」と勧誘する投資詐欺
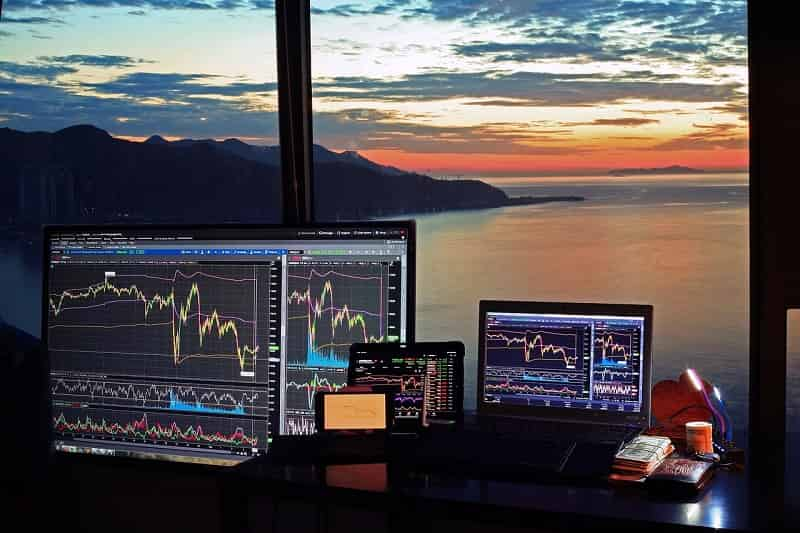
「簡単に儲かる」「元本保証」「今だけのチャンス」といった言葉で勧誘する詐欺です。
高齢者に投資用の口座を作らせ、多額の資金を振り込ませるケースがあります。
後になっても返金されず、連絡も取れなくなるのが典型的なパターンです。
儲け話には必ずリスクがあります。
少しでも怪しいと感じたら断る勇気を持ちましょう。
詐欺を仕掛ける側が情弱な高齢者を狙う理由
お金や資産を持っている人が多いから

高齢者は長年働いてきた分、貯金や年金などの資産を持っている人が多いです。
詐欺師はその資産を狙って、巧妙な言葉で近づいてきます。
「子どもや孫のために」と思ってお金を出してしまうこともあり、
その優しさが逆に悪用されてしまうのです。
自分の資産を守るためにも、冷静な判断と知識が欠かせません。
家族や周囲と情報共有が少ないから
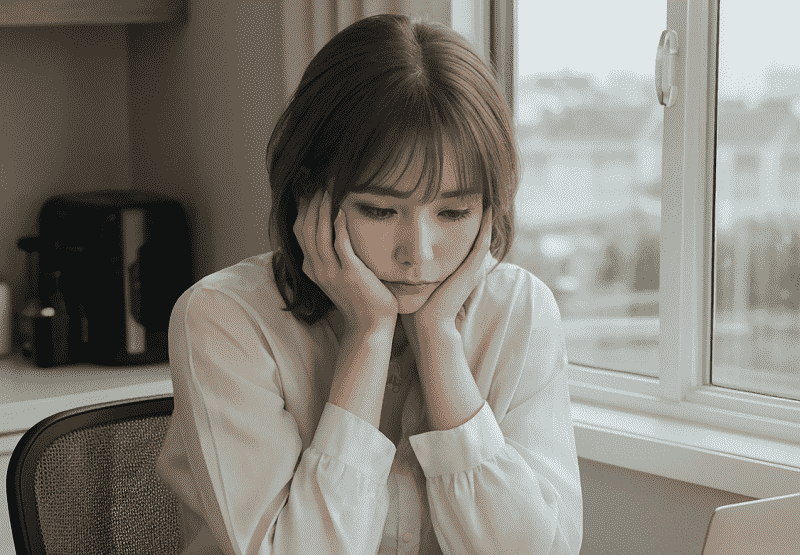
高齢者は日常的に誰かと情報を共有する機会が少ないため、
間違った判断を一人でしてしまいがちです。
「人に迷惑をかけたくない」「もう歳だから自分で解決しなきゃ」
と思い込んでしまう人もいます。
でも、相談することは迷惑ではなく、身を守るための大切な行動です。
身近な人との会話を増やすことが、詐欺予防の第一歩です。
被害に遭っても気づかれにくいから

高齢者が詐欺に遭っても、気づかれるまでに時間がかかることが多いです。
被害者自身が「騙された」と気づかないまま、何度もお金を渡してしまうこともあります。
また、詐欺師は「誰にも言わないで」と口止めをして、孤立させる手口も使います。
周囲が気づきにくいからこそ、定期的な声かけが大切です。
情弱な高齢者が詐欺を防ぐために知っておきたいこと
知らない番号からの電話には出ない

電話を悪用する詐欺が非常に多いため、知らない番号には出ないことが基本です。
留守電にしておき、用件があれば折り返すようにしましょう。
「非通知」や「見知らぬ携帯番号」からの着信は特に要注意です。
ご家族にも「知らない番号からは出ないようにしている」と伝えておくと安心です。

知らない番号は即スルーが鉄則!
「ATMでお金が戻る」は詐欺と知る
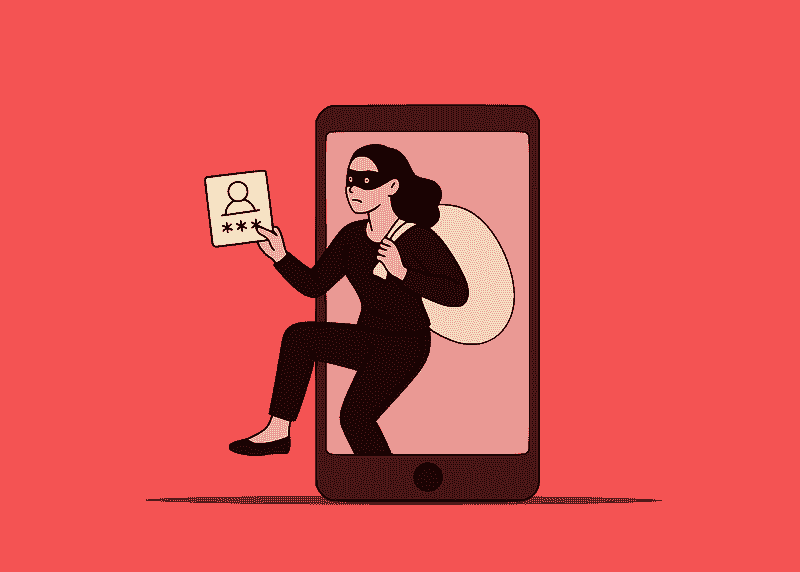
ATMでお金が返ってくることはありません。
「今すぐ近くのATMに行ってください」と言われた時点で詐欺です。
また、操作を教えるという電話もすべて嘘です。
役所や銀行が電話でお金の返金を案内することはないと覚えておきましょう。
お金の話が出たら必ず誰かに相談する
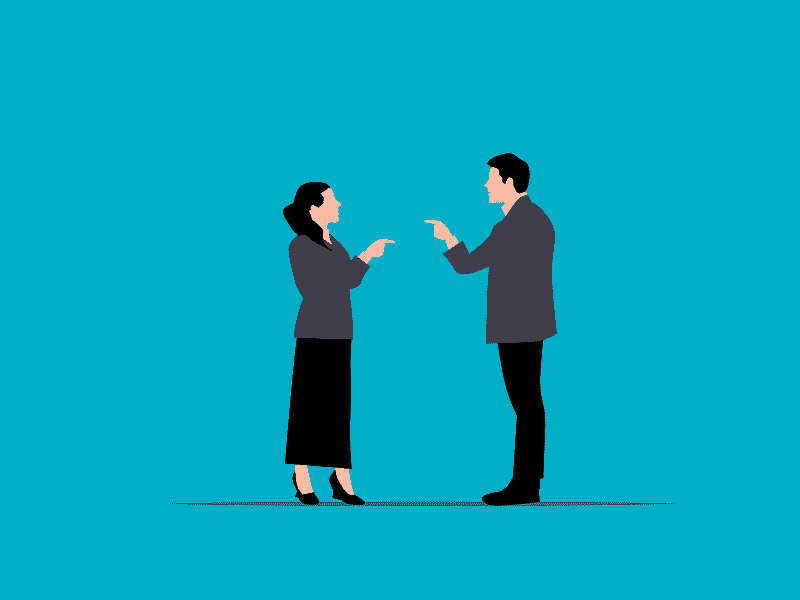
少しでもお金の話が出てきたら、すぐに誰かに相談することを徹底しましょう。
家族や近所の人、市役所や警察でもかまいません。
詐欺師は「誰にも言わないでね」と言ってきますが、それは騙している証拠です。
相談は、被害を防ぐ最も効果的な方法の一つです。
家族ができる!情弱な高齢者の詐欺被害を防ぐサポート方法
日頃からこまめに連絡をとる

詐欺師は「孤独」を狙います。
日常的に家族から連絡があるだけで、「相談しよう」という意識が芽生えます。
ちょっとした世間話でもいいので、LINEや電話でこまめなコミュニケーションを取りましょう。
「困ったらいつでも連絡してね」と一言添えておくのがポイントです。

孤独にさせない工夫が詐欺予防
実際の詐欺事例を一緒に共有する
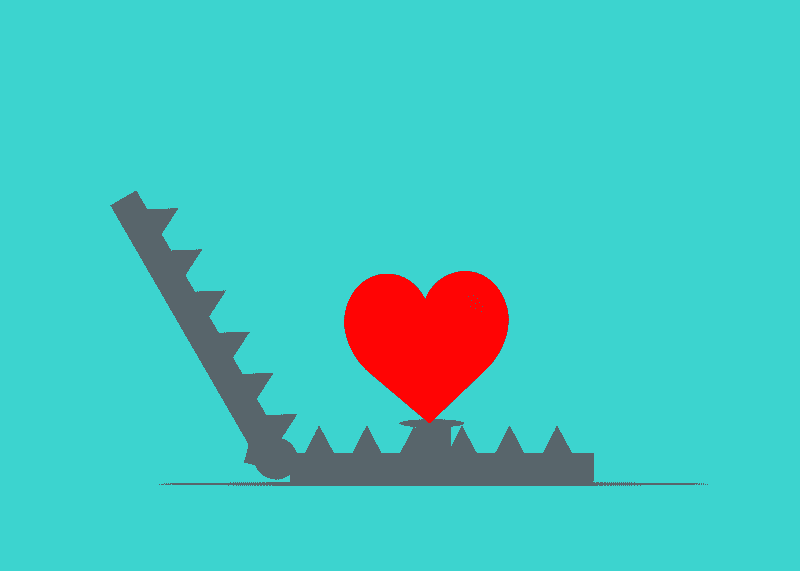
新聞やニュースで紹介されている詐欺事例を一緒に読んで、
「こんなことあるんだね」と話す時間を作りましょう。
一方的に注意するのではなく、会話の中で自然に情報を共有すると受け入れられやすくなります。
また、地域の防犯情報などを紙に印刷して渡すのも有効です。
「知っている」だけで、防げる詐欺はたくさんあります。
「怪しい」と思ったらすぐ連絡してもらう約束をする

「何かあったらすぐ連絡して」と言うだけでは足りません。
あらかじめ「こういう時は連絡してね」という具体的なパターンを決めておくと、
高齢者も行動しやすくなります。
たとえば「お金の話が出たら必ず相談する」「電話の相手が名乗らない場合は出ない」
などルールを共有しておきましょう。
「ひとりじゃない」と感じてもらえることが、詐欺防止につながります。

具体例で安心感UP!ルール作り大事
情弱な高齢者が詐欺被害に遭ったときの相談先と対処法
警察相談専用窓口(#9110)

全国共通の警察相談窓口です。
緊急ではないが「相談したい」「不安がある」という時に使えます。
最寄りの警察署につないでもらえるので、身近な情報を得ることができます。
通話料は有料ですが、迷ったらまずここにかけてみましょう。
消費者ホットライン(188)

「いやや!」の語呂で覚えやすい全国共通の相談窓口です。
消費生活センターにつながり、詐欺・契約トラブル・ネット被害など、幅広く対応してくれます。
相談は無料、匿名でも可能です。
少しでも「おかしいな?」と思ったら、迷わず電話してみましょう。
全国銀行協会の「振り込め詐欺救済法」対応窓口

被害にあった口座にお金を振り込んでしまった場合、
一定の条件を満たせばお金を取り戻せる制度があります。
すぐに銀行や全国銀行協会に連絡し、対応を依頼してください。
振込後すぐであれば、口座凍結や返金の手続きが可能になるケースもあります。
被害に気づいたら、1秒でも早く動くことが重要です。

「被害発覚後は即行動が命です!」
まとめ:情弱な高齢者が詐欺を防ぐために大切な知識と備え
最新の詐欺手口を家族と一緒に学ぶことが大切

情報は「知っているかどうか」が分かれ道です。
テレビやネット、新聞などから最新の手口を家族で共有する習慣を持ちましょう。
「自分には関係ない」と思わず、常に警戒心を持つことが重要です。
お金の話は必ず誰かに相談する習慣をつける

詐欺のほとんどは「お金」に関係しています。
お金を渡す、振り込む、契約するという場面では、
必ず家族や信頼できる人に相談するようにしましょう。
「迷ったら聞く」が、最大の詐欺対策です。
詐欺の連絡には「出ない・渡さない・信じない」が鉄則

電話に出ない、個人情報やお金を渡さない、そして知らない人を簡単に信じない。
この3つを守ることで、ほとんどの詐欺を防ぐことができます。
高齢者とその家族が協力して、安心できる生活を守っていきましょう。