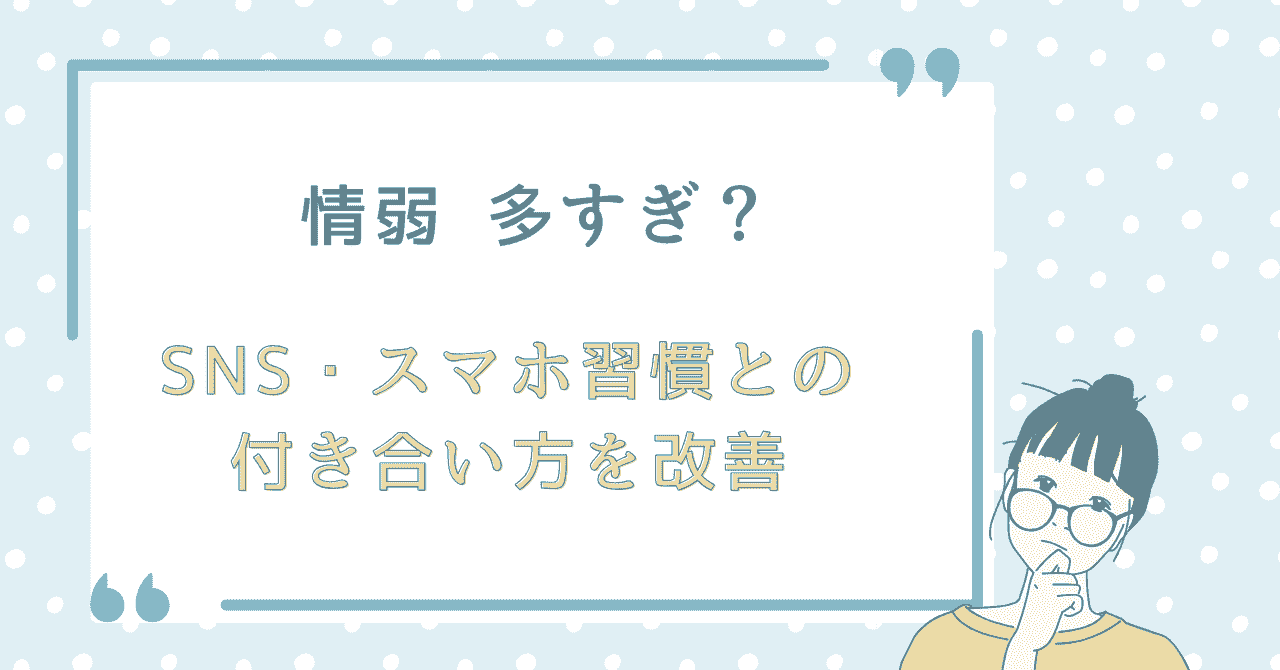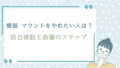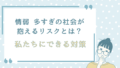情報があふれる現代において、「情弱(情報弱者)」という言葉がますます注目されています。
特に、SNSやスマホの使い方によって、知らず知らずのうちに正しい判断ができなくなる
「情弱」が社会全体で増えている現状があります。
本記事では、なぜSNSやスマホが「情弱 多すぎ」の社会を生み出すのか、
そしてその改善方法や向き合い方についてわかりやすく解説します。

知らないとヤバイ!今すぐ対策始めよう
情弱が多すぎる原因はSNSやスマホの使い方にある?
誰でも簡単に発信できるため情報の質に差がある
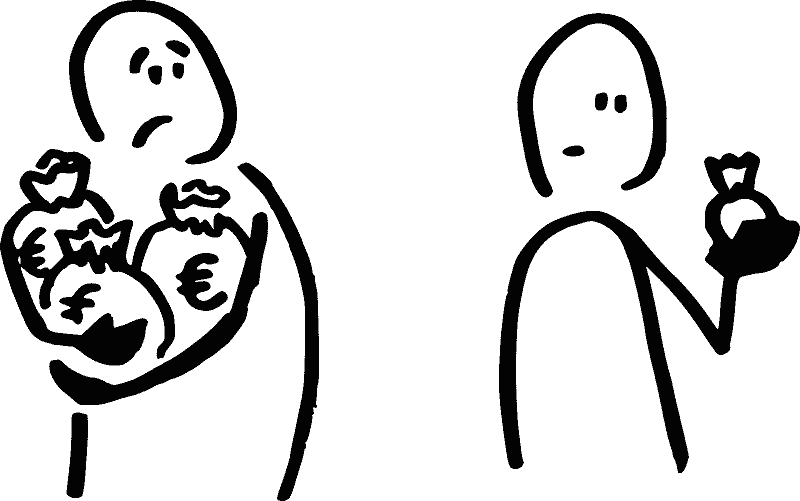
SNSでは、専門家でなくても誰でも情報を発信できます。
これは便利な反面、間違った情報や偏った意見が多く流通する原因にもなっています。
発信のしやすさは情報の質のバラつきを生み、それが情弱を増やす温床になっています。
拡散されやすい情報ほど過激・不正確なことが多い
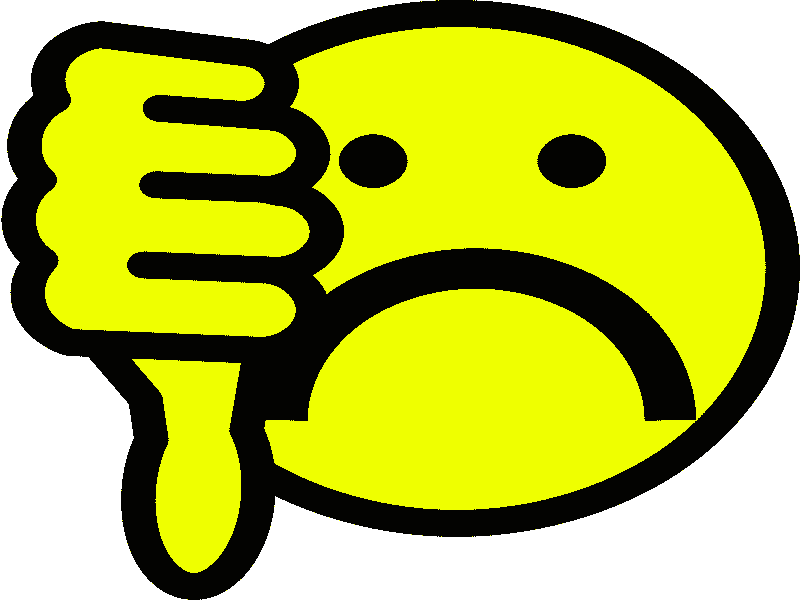
人の目を引くために、タイトルが過激だったり、感情的な内容だったりする投稿が広まりやすい傾向があります。
しかし、そうした投稿ほど内容の正確さが低く、誤解を招きやすくなります。
スマホで常に情報に触れることで取捨選択が雑になる
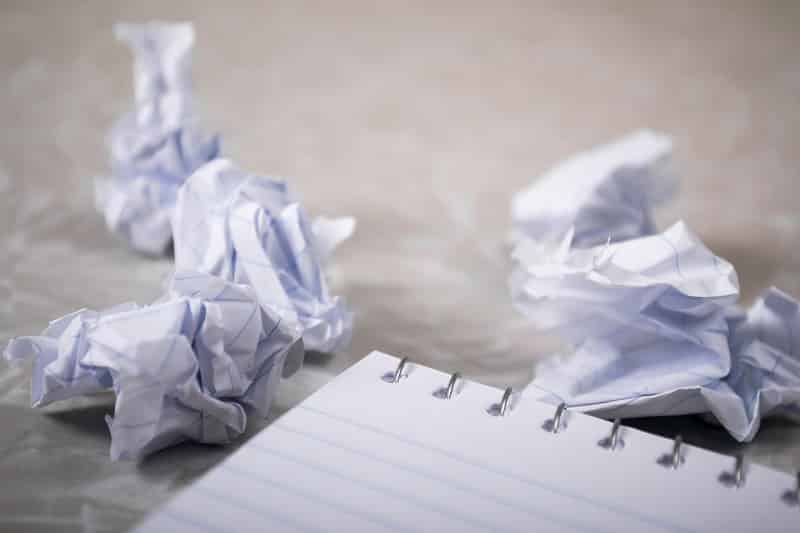
スマホはいつでもどこでも情報にアクセスできますが、
その便利さが「なんとなく読んで信じてしまう」危険を生み出します。
情報をしっかり考えずに受け取る習慣が、情弱の原因になります。
SNSの情報に流されると情弱が多すぎる社会になる理由
感情的な投稿が事実より広まりやすいから

怒りや悲しみなどの強い感情を伴う投稿は、共感されやすく、拡散されやすくなります。
しかしその一方で、事実に基づかない情報でも「感情の勢い」で信じられてしまうのです。

熱い投稿、信じる前に裏取りを!
バズった投稿が正しいと思い込んでしまうから

「いいね」や「リツイート」が多い投稿=正しいと思ってしまう人が増えています。
人気のある投稿=正確な情報とは限らないため、注意が必要です。
アルゴリズムが偏った情報ばかり見せてくるから
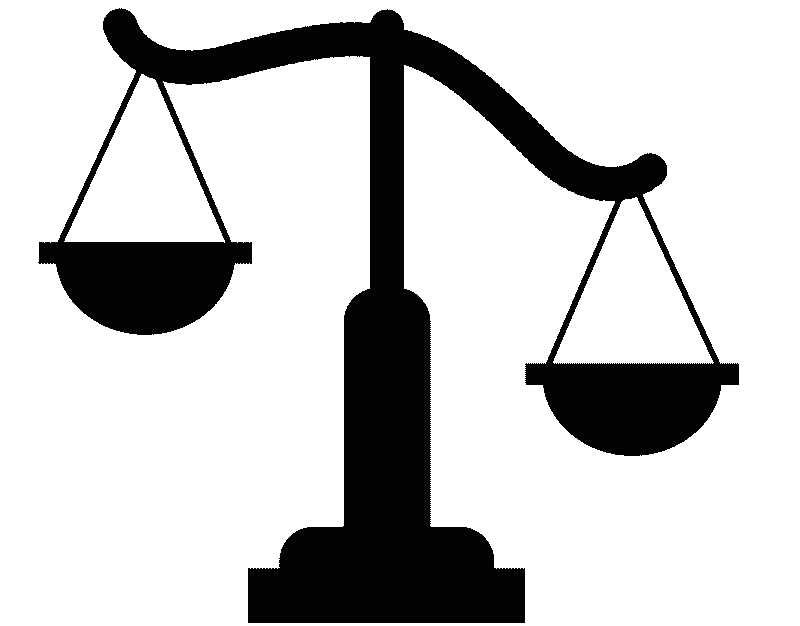
SNSはユーザーの好みに合わせた投稿を優先的に表示します。
これにより、考えが偏った情報ばかり目に入る「情報のかたより」が生じます。
結果的に、他の意見を知らないまま、間違った情報を信じ込む情弱になりやすくなります。
スマホ依存が情弱を多すぎにしてしまう仕組みとは
短時間で大量の情報に触れすぎて判断が浅くなる

スマホをスクロールするだけで、数秒ごとに違う情報が目に入ります。
そのため、一つひとつの情報を深く考えずに流し見してしまいます。
これでは、正しいかどうかの判断力が養われません。
通知やおすすめ表示に振り回されやすくなる
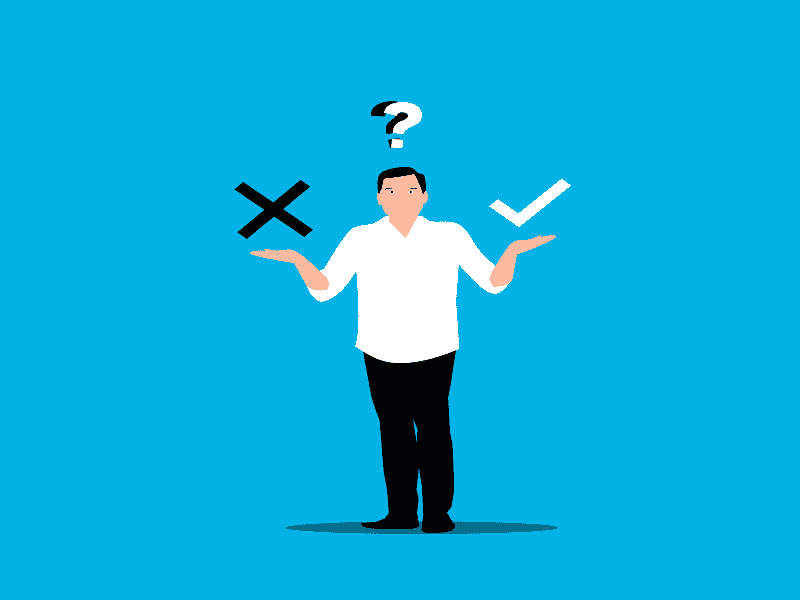
通知が来るたびにスマホを見る癖がつくと、集中力が切れやすくなり、
情報の質を判断する余裕もなくなります。
おすすめ機能は便利ですが、あくまで機械が選んだものであり、内容が正しいとは限りません。

私も通知オフで集中力キープしてます!
長時間使用で注意力や集中力が低下する

スマホを見続けると脳が疲れ、思考力や判断力が落ちてきます。
これは特に夜間の使用に顕著です。
情報を見るだけでなく、考える力そのものが落ちることで、情弱になりやすくなります。
情弱が多すぎる現状を生まないためのSNSリテラシーとは
情報の出所や発信者の意図を考える習慣を持つ
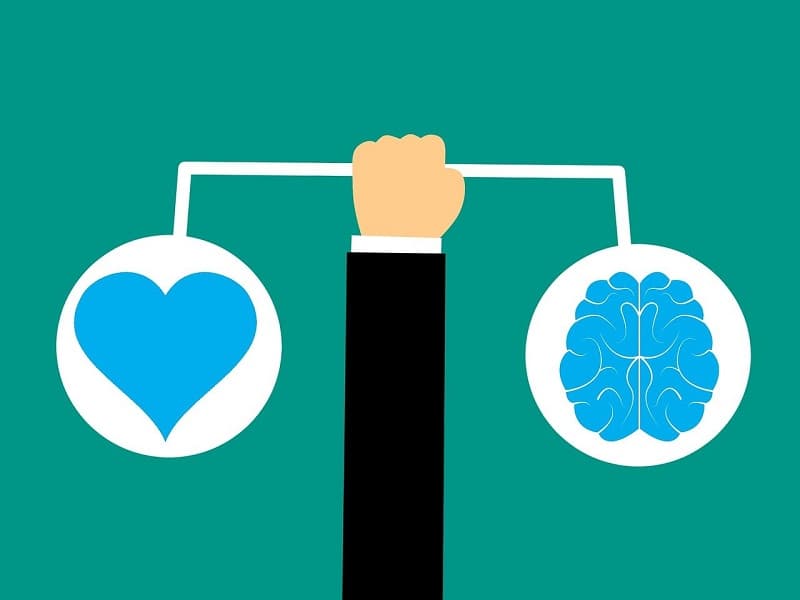
投稿した人は誰か?その人の目的は何か?を考える習慣をつけると、
誤情報に振り回されにくくなります。
「誰が」「なぜ」発信しているかを見極めることが第一歩です。
投稿の「共感」より「根拠」を重視して見る
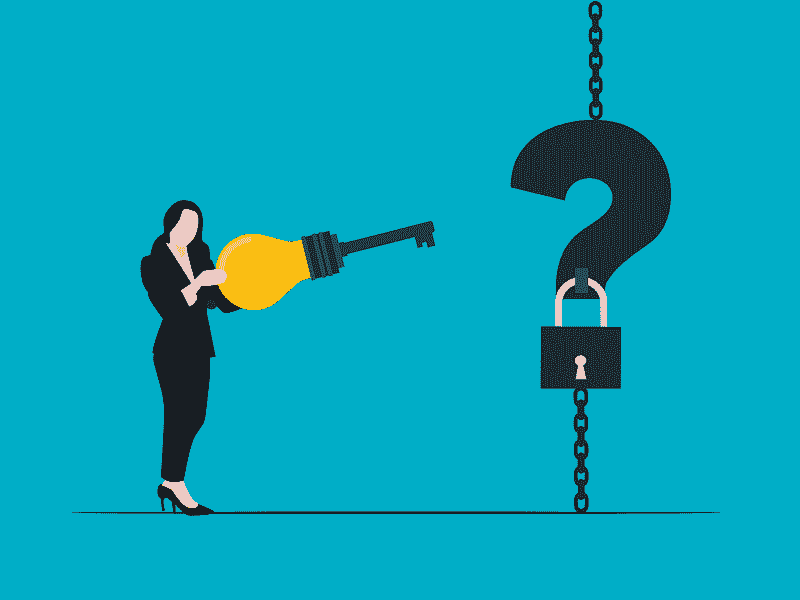
「わかる!」「すごい!」と思っても、まずは「それって本当?」と冷静に考える癖をつけましょう。
エビデンスや資料の有無をチェックすることが、正確な判断につながります。
フェイクニュース対策のサービスを活用する(GoHoo、FIJなど)

「GoHoo」や「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」などのサイトでは、
誤情報やデマの検証がされています。
こうしたツールを活用することで、自分の判断に自信が持てるようになります。

デマに惑わされない自分に!
スマホとの正しい付き合い方で情弱を多すぎにしない工夫
SNSの利用時間を1日〇時間など制限する
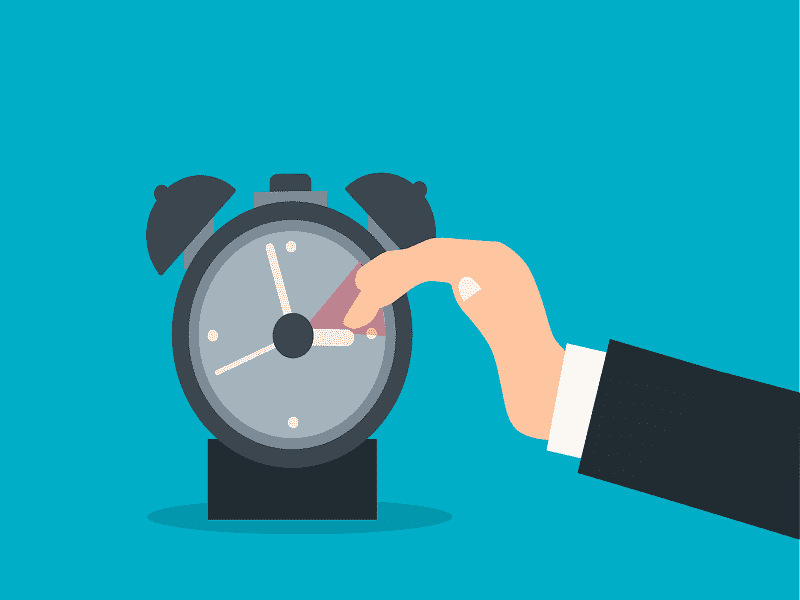
あらかじめ使う時間を決めておくことで、無駄な情報に触れる時間を減らすことができます。
スマホの設定で利用時間を制限できる機能を活用するのも効果的です。
スマホを使わない時間帯(デジタルオフ時間)を設ける

寝る1時間前はスマホを見ない、食事中は触らないなど、自分なりの「スマホオフルール」を決めて実践しましょう。
情報に支配されず、心と頭を休める時間が大切です。
情報を受け取るだけでなく、自分で調べる習慣をつける
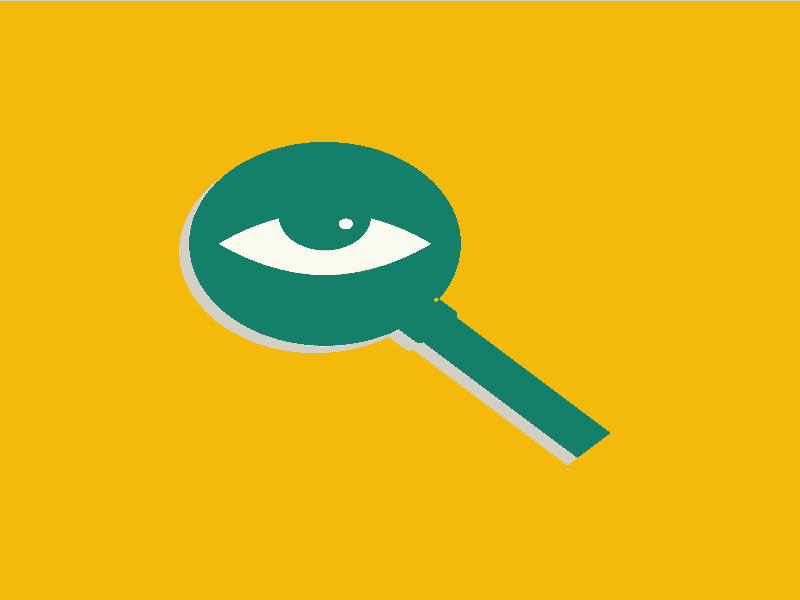
SNSで知った内容について「本当かな?」と検索して調べてみることが、判断力を養います。
「受け取るだけ」で終わらせず、行動を伴う情報習慣が、情弱脱却への第一歩です。
子どもや若者が情弱にならないSNS・スマホ習慣の教え方
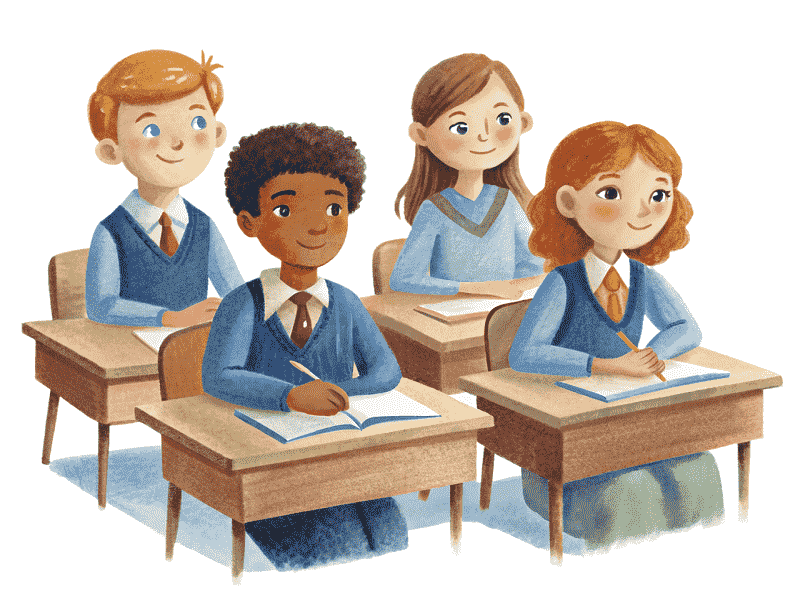
次世代を担う子どもや若者たちにこそ、正しい情報の扱い方を早くから教える必要があります。
家庭や学校での情報教育は、今後の社会全体の健全化にもつながります。
情報の見方やリスクを親子で話し合う時間を作る

「それって本当かな?」「この情報、どう思う?」と日常的に会話をすることで、
子どもも考える力を身につけます。
親自身も一緒に学ぶ姿勢を見せることがポイントです。
SNSで見た情報を「本当かな?」と一緒に検証する

子どもがSNSで見た情報に驚いたり、信じたりしているときは、頭ごなしに否定せず、
一緒に確かめてあげましょう。
調べる過程を一緒に体験することが、情報リテラシー教育の実践になります。

驚きも不思議も、一緒に探検しよう!
文部科学省の「情報モラル教材」などを活用して教える
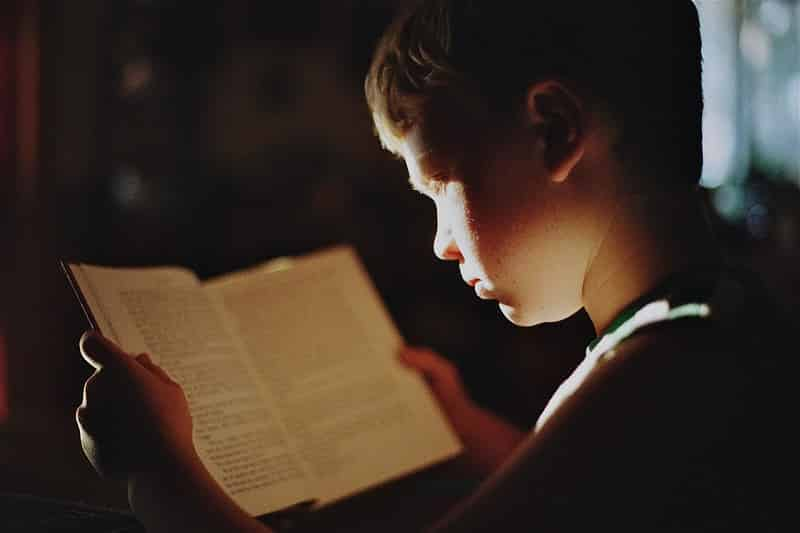
文部科学省や総務省などが出している教材には、
ネットやSNSに関する正しい知識がわかりやすくまとめられています。
教材を活用しながら、家庭で「学び合う」時間を設けることが効果的です。
情弱が多すぎる社会に向き合うための個人の行動と意識改革
「知った気になる」前に複数の視点で情報を確認する
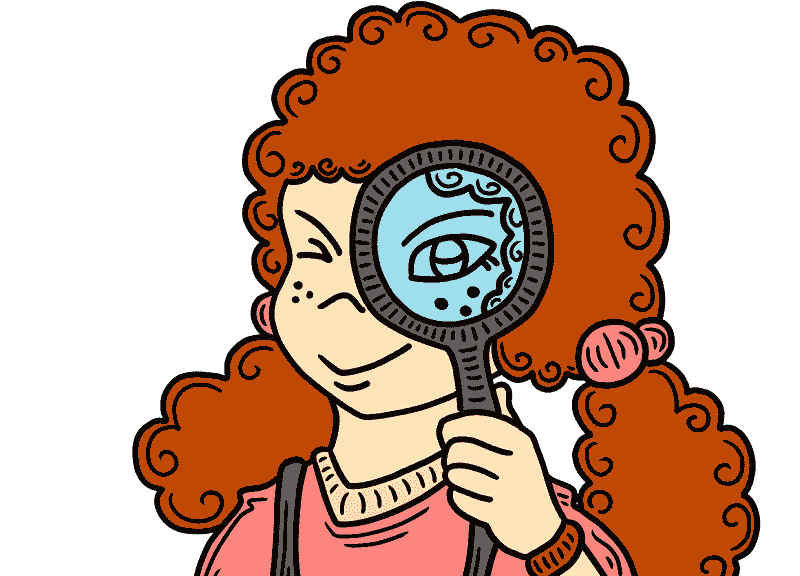
1つの投稿や記事だけで満足せず、別のサイトやメディアでも調べてみる癖をつけましょう。
いろんな視点を知ることで、自分の判断も確かなものになります。
情報の質を見極めるために常に学び続ける姿勢を持つ
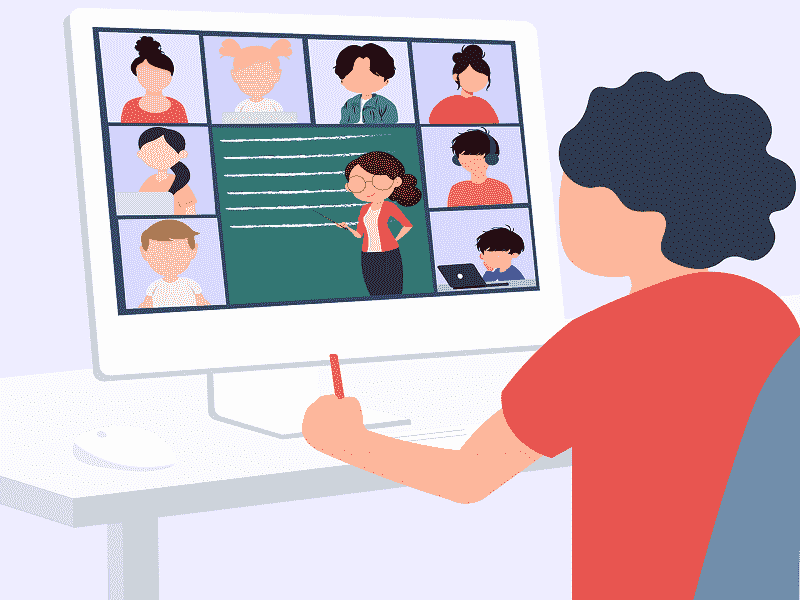
情報リテラシーは一度身につけば終わりではありません。
時代や技術が変化する中で、学び続けることが必要です。
読書や信頼できるニュース、専門家の発信などを日常に取り入れましょう。
情報を共有・議論できる仲間やコミュニティを作る

一人で考えるよりも、複数の人と話し合うことで新たな気づきが得られます。
信頼できる仲間と情報を共有し合うことが、情弱から抜け出す大きな力になります。
まとめ|情弱 多すぎを防ぐためのSNS・スマホ習慣の見直し
SNSやスマホは「使われる」のではなく「使いこなす」意識を持つ

通知に反応するのではなく、自分で選んだタイミングで使うことが大切です。
スマホに依存しない生活を意識的に作ることが、情報リテラシー向上への第一歩です。
正しく情報を扱う力は日々の習慣で身につく
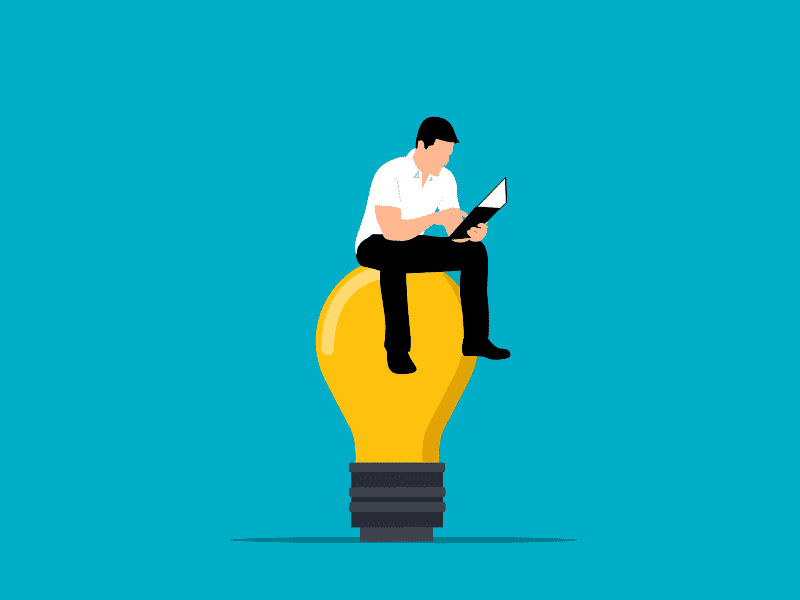
情報の出どころを確認する、複数の情報源を比べる、感情に流されない。
これらの習慣を日常に取り入れましょう。
毎日の「見る」「調べる」「考える」の積み重ねが情弱脱却へのカギです。
未来の自分や子どものために、今からできる工夫を始めよう

情報社会を生き抜くためには、大人も子どもも常に「学ぶ」姿勢が必要です。
今できることを一つずつ積み重ねることで、情弱が多すぎる社会に歯止めをかけられるはずです。